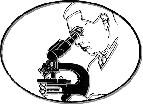 |
||||||||||||||||
|
平成21年度吉田富三賞を受賞して 名古屋市立大学大学院医学研究科 教授(腫瘍・免疫学講座) 上田 龍三
■平成21年度 吉田富三賞を受賞して■ この度、期せずして平成21年度の栄えある吉田富三賞を受賞させて頂き感謝いたしております。日本癌学会 会員の皆様、特に、ご推挙頂きました選考委員の皆様には厚く御礼を申し上げます。私は昭和44年名古屋大 学医学部を卒業以来、がんの治療や研究を名古屋大学、スローンケタリング癌研究所、愛知県立がんセンター 研究所、そして現在の名古屋市立大学と約40年開続けて参り、この3月で満期退職を迎えます。この節目に当 たり、がん研究者として最も評価の高い吉田賞を受賞できましたことは癌研究者の一人として感激ひとしおでご ざいます。 今回の受賞理由は「ATL(成人T細胞性白血病・リンパ腫)を始めとしたT細胞性血液がんに対する独創的抗 体療法の基礎研究成果を臨床研究で証明し、我が国における腫瘍免疫療法発展に大いに貢猷された。」と評 価して頂きました。この機に私が一貫して行なってまいりました「抗体を用いたトランスレーショナル・リサーチ」 の苦楽の一端を皆様にご紹介させていただきます。 ■腫瘍免疫の研究を開始したきっかけ■ 私は大学の白血病グループの一員として化学療法や黎明期の骨髄移植を若さと情熱で頑張っておりました が、当時の医学では解明できてないことが多く、日夜の奮闘の甲斐もなく多くの侮しい思いをしたものでした。恩 師故 山田一正先生(名古屋大学名誉教授)の推薦を受け、1976年にニューヨークにあるスローンケタリング癌 研究所のロイド・オールド博士(当時副所長)の研究室に「ヒトがんで腫瘍免疫は成り立つか。端的には、ヒトが んにがん特有の抗原(腫瘍特異抗原)の存在が証明できるか」という基本的な命題を受け研究を開始いたしまし た。マウスLy抗原や現在癌や炎症の病態や治療において重要な腫瘍壊死物質(TNF)の発見者でもあるオール ド先生はサイエンスー筋の誠実で情熱あふれる研究者でした。研究室には世界各国から腫瘍免疫を勉強したい 研究者が参集しており、日本からも東大、北大、九大、名大はじめ企業などからの俊英で大いに賑わっていまし た。当時オールド研究室の”ヒトがんプロジェックト”を纏めておられたのが第16回吉田賞受賞者の高橋利忠先 生(愛知県がんセンター名誉総長)であり、現在日本のがんワクチン研究の先駆者として活躍されている珠玖 洋先生(三重大学特任教授)した。 ■腎がんをなぜがん抗原探索の対象に選んだか■ 最初に、なぜ私がヒト腫瘍特異抗原の検出の対象がんとして腎臓がんに取り組むことにしたかをご説明したい と思います。我々のがん抗原発見の戦略は、腫瘍特異抗原の検出にがん患者さんご自身にできたがん細胞に 対して自家抗体を有しているか否かを科学的に追及することです。そのような抗体が見出されば、その抗体は 自己がん細胞にのみ反応する腫瘍特異(固有)抗原か、腎臓がんに共通の抗原(腫瘍特異共通抗原、現在は がん精巣抗原のCancer Testis antigenと命名)か、もしくは分化抗原、組織特異抗原、その他ウイルス由来タ ンパク、各種の融合タンパク由来の抗原なのか等を詳細に解析し、更にこの同定された抗原ががんの発症とか 増殖また転移などとどのような関係があるのか、最終的には治療応用への可能性を追求することでありました。 腎臓がんを選択したのはがん臨床において、腎臓がんは時に治療しなくても自然に退縮する症例の報告があ り、免疫の関与が示唆されるがんであること。我々の戦略では患者さんのがん細胞を試験管で培養して、患者 さんのがん細胞に存在している多くの抗原の中からがん特有の抗原を探すことでした。腎臓がんは試験管内で 育てること(組織培養)が比較的容易であったこと、当時の腎臓がんの患者さんは、治療として腎臓摘出術をう けましたが、手術で取り出したがん組織には必ず患者さんの正常な腎臓の組織の一部も含まれております。こ の正常部分の腎臓の細胞が短期ならほぼ100%近く培養ができ、実験に耐えるだけの量の細胞培養が可能で あったことは、解析を進めるうえで、非常に有利であったわけです。がん細胞解析のコントロール細胞として、単 に患者さんの皮膚の細胞(培養が容易)、や血液細胞のみでなく、腎臓がんの発生母細胞と考えられる正常腎 上皮細胞が使用できたことは、一般の固形がん(上皮系のがん)の中では最大の利点であり、強みでありまし た。さらにスローン・ケタリング癌記念病院の泌尿器科部長は世界に冠たるウイットモア博土で世界中から腎が んの手術を希望した患者さんの手術が後を絶たず、研究資料や資金援肋が十二分にあったことなどが決め手と なりました。 ■モノクローナル抗体との出会い■ 精力的に研究を進めていくうちに、いくつかの腎がんに関係する抗原の検出に成功できましたが、この抗原の 科学的な同定となると、当時の生化学的手法では至難の業でした。研究所ではケラー博士とミルシュタイン博 士がScience誌に1975年(私の留学の前年)に発表したマウスモノクローナル抗体作製法をいち早く導人し、こ の作製法を追試したり、改良して希望の抗体作製に鎬を削っていました。私も我々が血清学的に複雑な吸収実 験を駆使して患者さんの少ない血清から同定した腎がんの腫瘍関連抗原に対するモノクローナル抗体の作製に 成功すれば、力価の高い、無限の抗体量を用いた抗原解析は飛躍的に進み、患者さんに抗体療法の実用化も 時間の問題であると、本当に勇気づけられたことが昨日のことのように思い出されます。それからの研究室はこ れまでの血清学的解析に加えて、解析により腫瘍抗原を保持している細胞をマウスに免疫して、試行錯誤の 中、モノクローナル抗体の作製に文字どおり日夜精励したものでした。抗体作製の過程からの新しい抗原系の 発見や自家血清から同定してきた抗原系との異同などでいくつかの成果を論文にまとめその後の研究は後継 者に任せて4年開の留学生活を終えました。 ■治療抗体を求めての臨床研究■ 1980年に帰国し、愛知県がんセンター研究所化学療法部に所属することになりました。当時は日本でもモノク ローナル抗体は正に「魔法の弾丸」と称され、商社までが抗体産生に参入するという時代でした。研究所初期の 間は白血病、リンパ腫、肺がんを対象に臨床の診断や治療に役立つモノクローナル抗体の作製に若い日本の 優秀な大学院生や研究者と一緒にとても多くの興味ある抗体の作製に成功したものでした。詳細な解析の中で 多くの特異性の高い抗体は診断や実験の材料としては有用な抗体でしたが、抗体自身がマウスで作製したマ ウスの血清成分であったこと、がんに対する特異性は高くても全く予期しないヒトの正常組織と交差反応を認め ることが多くとても人体に直接投与できるものではありませんでした。我々はリンパ性白血病に非常に特異性の 高い抗原(CALL抗原、後のCD10)に対する抗体の作製に成功し、この抗体を自家骨髄移植の際に、患者さん が化学療法でほぼ治癒(寛解)した時期に、自身の採取した骨髄液に残存している可能性のある白血病細胞を この抗体と反応する細胞を除去することにより、より綺麗な骨髄幹細胞を移植することができ、少しでも白血病の 再発を防ぐ治療法を試みたものでした。このプロジェックトが、我々が唯一治療として抗体を用いたものでした。し かし、この治療法は飽くまで、体外での処理による治療で患者さんに直接抗体を投与する治療法ではありませ んでした。 当時分子生物学が飛躍的に進歩して、抗体作製も遺伝子工学の技術により、マウスとヒトのキメラ抗体や抗 体分子のほとんどがヒト由来で抗原認識部位のみがマウス由来と言うヒト化抗体、さらには目的の抗原に対し て全抗体分子をヒト由来であるヒト抗体の作製に成功したことにより、俄かに患者さんに安全に直接投与できる 抗体療法が現実のものと期待されました。そして1997年にアメリカのFDA(米国医薬品機構)が抗CD20抗体(リ ツキサン)の悪性リンパ腫への臨床使用を承認したことで、がんの抗体療法の新しい幕開けが始まりました。 ■抗CCR4抗体との出会い■ 1995年に名古屋市立大学第二内科教室に招聘されてからは、一段と全国ネットワークを広げて、白血病、リン パ腫、骨髄腫などの造血器腫瘍と肺がんの臨床研究を進めました。悪性リンパ腫は腫瘍細胞の性質によりT細 胞性とB細胞性のリンパ腫に大別されます。B細胞性リンパ腫の研究は欧米で盛んに行われており、化学療法 のCHOP療法や抗体療法のリツキサンなど一定の成果が出ておりました。日本に多いT細胞性リンパ腫は病態 が多彩で、治療が困難にもかかわらず治療研究が進んでいませんでした。我々は正常なT細胞の機能や特徴 を有しているT細胞性腫瘍の探索をリンホカイン、ケモカインやそれらのレセプター等の抗体や遺伝子発現など の解析から検討しておりました。ケモカインリセプターの一つであるCCR4が、日本で1977年に新しい疾患単位 として当時京都大学におられた高月清先生方により発見、提唱された成人T細胞性白血病・リンパ腫(ATLL)に 高頻度に発現していることを見出しました。このATLはウイルス感染で発症することを2009年度の文化勲章を受 賞された日沼頼夫(京都大学、熊本大学名誉教授)先生、そのウイルスの全塩基配列は第8回吉田賞の受賞 者である吉田光昭先生(東京大学名誉教授)方により決定されるなど、日本の研究者による素晴らしいお仕事 で病気の本態が解明されてきております。しかし、残念なことにATLは長期間の潜伏期を経て、ひとたび発症す ると臨床的には白血病の中でも最も治療困難な病気で、標準的な治療法も確立されていないという難病です。 我々はCCR4がこの難治性腫瘍であるATLL、末梢性T細胞性腫瘍(PTCL)に強く発現していること、ATLの 細胞起源を明らかにするとともに、CCR4陽性の白血病やリンパ腫の患者における日和見感染症が多いことに 関連する等、臨床でのATLの病態形成に関する役割につき研究結果を報告してまいりました。そこで、CCR4を 用いた抗体療法に正面から取り組み、協和発酵研究所が開発した糖鎖の修飾(低フコース化)法を本CCR抗体 に適応することにより強力な抗体依存性細胞性障害(ADCC)活性と抗腫瘍効果の発現を試験管内でもマウスを 用いた治療実験でも実証できました。次いで、抗体の安定性や詳細な毒性試験を積み重ね、臨床導入をめざし アカゲザルを用いた投与実験も完遂して、臨床導入に必要な前臨床実験データを2006年までに全て揃えること ができました。 ■日本発のがんに対する抗体療法の開始■ 上記の一連の研究成果に基づき、がんに対する抗体療法としては本邦初の臨床第1相試験開始を目指して、 プロトコール作成の検討会を頻繁に行いました。最も重要な課題は抗体の投与スケジュールの決定と初回投与 量の設定でした。折しも英国で抗体療法の治療研究を試行中に健常な方が抗体注入直後に、発熱、意識混 濁、呼阪不全、多臓器不全などの重症な副作用に見舞われ集中治療室で加療をせざるを得なかった報告が世 界中に流れ研究者を震憾させたものでした。その影響で新薬研究、特に抗体治療に関しての予期せぬ副作用 に神経を尖らしている時期だったのです。国立がんセンター中央病院、愛知県がんセンター病院それにATL患者 さんの多い九州地区で多くの患者さんを治療しておられる九州がんセンター、長崎大学、鹿児島大学、鹿見島 市にある今村病院分院の協力を得て、遂に、平成2006年8月から再発または治療抵抗性のCCR4陽性T細胞性 腫瘍に対して抗CCR4抗体療法の臨床第1相試験が日本で開始できました。ちなみに投与スケジュールは1週 間に1回、4回投与、初回投与量は前臨床の結果を踏まえ、現在一般に投与されている抗体量の1000分の1以 下である0.01mg/kgというごく微量から暫時増量する方法で開始しました。(Clinical Trialsgov Identifier: NCT00355472) ■予想以上の治療効果に嬉しい驚き■ 最初の1例目の緊張感は忘れることができません。患者さんに投与した後、時間単位での問い合わせに「何 事もありません」との報告に胸をなで下ろすとともに、抗体量が0.1mg/kgだから、体での濃度は全く希薄なもの で水同然で、何か起こるという心配の方が可笑しいと納得したものでした。無論、治療効果はありませんでし た。二例目の急性型の症例では抗体投与直後に軽い悪寒、発熱があり、患者さんに投与したのはやはり水で はなく抗体であることを認識させはしましたが、0.01mg/kg4回投与後3週目の効果判定時には治療効果はあり ませんでした。しかし、化学療法後、再発の急性型ATL症例で皮膚には細胞浸潤による皮疹を伴い、画像上で は椎体が腫瘍浸潤のため解けている患者さんが治療開始後7週間、病態が安定しており決して悪化しなかった ことは、ATL患者さんをよく診る血液臨床家にとっては驚きでした。ひょっとしてこの極めて微量の抗体量でATL に効いているのかもしれないという期待感を持たせたものでした。もっと感動的だったのは同じ投与スケジュー ルの3例目でした。3例目は白血球が1万近くあり、その中の約20%がATL細胞で占められている典型的な急性 型の症例でした。投与直後に比較的強い悪寒、戦慄、高熱をきたし、主治医団は大いに気を病み、注意深く観 察しておりました。夕方投与が終わり、翌朝の検査では白血球数が約半分の五千に減少しているばかりでなく ATL細胞が既に末梢血からは消えていたのです。1週間後の2回目の投与の前採血では僅かながATL細胞が 散見されましたが、今回も翌朝の検査では血液中からATL細胞は全て消失しており、以後7週間の観察中は全 く健常人と変わらぬ寛解状態を維持でき、「我々の抗体療法で現在の治療に無効のATL症例に有効であっ た」、この感激は何物にも代えがたいものでした。その後計画に沿って3名毎の患者さんに投与量を1.0mg/kgま で増量したところ、大きな副作用もなく、順調に治療研究が完遂できました。 この厳密な臨床第1相試験では、再発または治療に抵抗性のATL症例などの従来の化学療法が無効な16例 に対してCCR4抗体単独による治療を行い、7週間後の効果判定時期に5例(31.3%)が著効と判定されまし た。リンパ腺の縮小効果が判定基準には達してはなかったが、臨床的に有効と考えられる症例二例を加えると 実に44%の症例が抗体療法の恩恵を受けたことになります。更に驚いたことに、第2例目はその後1年後の判 定では皮膚浸潤だけでなく、骨の融解していた病変まで完全に消失しており、以後、再発のない状態がほぼ3 年維待されております。有効例のうち5例は既に観察期間が500日以上に達しており現在のところ再発の兆候 は認めておりません。このように、これまでのATLへの治療経験からは想像もっかない有効例がえられ、現在、 ATLへの治療薬として承認を受けるべく第2相試験を順調に展開しております。この経験で注目していることは、 研究室で行われた前臨床研究結果に沿って行った臨床試験において、臨床効果が科学的に実証(proof of concept)されたことです。このような貴重なトランスレーショナル・リサーチを本邦で展開できたこと、素晴らしい 多くの仲開に恵まれたことを感謝すると共に、臨床研究者として本当に幸運でもあったと思います。 ■CCR4抗体の免疫療法への新たな展開■ CCR4抗体が反応するケモカインレセプター4(CCR4)は正常な細胞ではリンパ球の中、生体の免疫バランスに 重要なCD4陽性CD25陽性の制御性T細胞(Treg 細胞)に強く発現していることを見出し報告しました。教室で は、ホジキンリンパ腫のっ腫瘍組織では多くのリンパ球が集族している病態に興味を持ち解析したところ、これら の反応性リンパ球は主に、ホジキンリンパ腫細胞が分泌するリガンド(CCR4分子と特異的に結合する物質)に より遊走させられたCCR4分子が陽性のTh2細胞とTreg細胞であることを明らかにしました。腫瘍細胞の周囲に 引き寄せられたTreg細胞は宿主からの腫瘍免疫による攻撃を回避し、腫瘍自らの生存に好都合な環境を作り 出していることも明らかにしました。そこで、ヒト免疫療法の実験モデルを免疫不全マウス(NOGマウス)で作り治 療実験したところ、現在期待されているペプチド・ワクチン等を用いる免疫療法の際に、抗CCR4抗体を投与する ことによってCCR4分子を発現するTreg細胞を腫瘍細胞周囲から除去できる可能性を示しました。これらの結果 は、腫瘍周囲に集まっているTreg細胞は腫瘍細胞と戦うCTL細胞効果の抑制を解除させて免疫による抗腫瘍 効果の増強に応用する方法として、今後の腫瘍免疫療法のひとつの重要な方向性を示していると確信しており ます。 ■おわりに■ 私の30年以上にわたる抗体研究の中で、ATLに対して初めて臨床利用可能な抗体に遭遇できたことは何より の喜びです。そして、長年の夢が抗体療法、腫瘍免疫療法として臨床の場で発展することを楽しみにしておりま す。ATLは日本の臨床家により病気が発見され、日本の研究者によって病因が明らかにされ、その本体ウイル ス遺伝子の全構造も決定されました。日本の西南部に多いATLの治療に確立したものは無く、臨床的に非常に 難渋している疾患ですが、従来の治療法と異なる抗体療法と言う選択肢を日本から提唱できることは研究者冥 利に尽きます。吉田富三先生は「がん研究の究極の目的は不幸な難病を克服するためにある」と述べておられ ます。現在のトランスレーショナル・リサーチ(TR)の原点であると改めて先生の研究精神に敬服するしだいで す。私の汗をかいた臨床経験や拙い研究経験から、TRに関しては臨床現場における科学的視点からの問題点 や疑問点を基礎研究者にフィードバックして解決する、即ちリバーストランスレーショナル・リサーチの必要性、重 要性を強く訴えておきたいと思います。また日本でTR研究を推進するには単に研究者の個人的な努力に依存 するのでは無く、前臨床研究や臨床試験に係わる色々な立陽の専門集団が連携をとりチームとして推進すると 共に、省庁間を超えた国家的支援が必須と考えております。それにつけても“トランスレーショナル・リサーチ”と いう言葉は医療者目線の言葉であり、参画してくださる患者さんからの目線の言葉とは思えない節があります。 日本語を大切になさり、漢字仮名交じりの表記法を主張し続けてこられた吉田富三先生からどのような日本語 表現が適切かご教授願えないことを残念に思います。 (平成22年2月吉日) 【受賞関連論文】
|