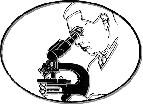 |
||||||||||||||||
|
吉田富三先生に出会った癌化学療法センター赴任 財団法人癌研究会・癌化学療法センター所長 吉 田 光 昭
私は、吉田富三先生に直接お会いしたことが無い。若い世代なのではなく、遅れてがん研究の世界に参入した からである。それゆえ、私の吉田富三先生のイメージは写真である。先生の写真にはなかなか魅力的なものが 多いが、癌研の菅野晴夫先生の部屋に飾ってあった(今は別の部屋にある)柔和なお顔の写真には、特別に惹 かれる。穏やかな表情でありながら、奥深い人柄を感じるせいであろう。ずっと以前にお聞きした菅野先生の話 によれば、土門拳氏が二百ショットに余るシャッターを切り、その中から選び抜かれた一枚なのだそうだ。写真 の難しさは、撮影ではなくて、良いものを選び出す目であると教わったことがある。 若かりし頃私は、長く癌研で仕事をさせていただいたこともあり吉田富三先生にまつわる逸話を聞く機会に恵ま れた。それ故であろう、先生の偉大さを良く知っているように感じるが、実は大きな間違いである。ご子息の吉 田直哉氏がお書きになった「がん細胞はこう語った」が出版されたときに、引き込まれるように読んだものであ る。そして大きなインパクトを受けたものである。先生に直接お会いしたことがない私の印象は、この著書による ところが多い。 吉田富三先生にお会いしたことも無い私が、俄仕込に先生のことを書き始めたのには理由がある。昨年秋にな るが、私は思いもかけないことに、財団法人癌研究会・癌化学療法センターの所長職を拝命した。同じ研究室 の仲間でもあった故鶴尾隆所長の後を引き継ぐ役割である。私は、長い間ウイルス発がんと取り組んできたも のの、がんの化学療法に直接向き合ったことはなかった。こじつければ、官職を退いたあと製薬企業に移り抗 がん剤の創製に関ったことくらいである。そこで遅ればせながら、癌化学療法センターの歴史を紐解いてみたわ けである。このセンターは吉田富三先生ががん治療の将来を深く洞察され、創立されたものであると言う。何た ることかとお叱りを受けるであろうが、初めて知った次第である。私のような方もおられるかもしれないので、我 が新知識を少々披露してみる。 癌研究会百年史によれば、 吉田富三先生はかねてより、「がんは局所疾患ではなく全身疾患である。手術や放射線治療で局所は治療し ても、どこに散っているか判らぬがん細胞を片付けねば完全治療とは言えぬ。有効な薬剤を全身に流すことに よってのみ、このことは可能である。従って、化学療法は単に外科・放射線に次ぐ第三の方法ではなく、がん治 療の最終手段である」 と言う考えを持っておられたと言う。吉田富三先生は、吉田肉腫の発見者として、また、がんは一つの細胞がク ローンとして増殖することを初めて示した研究者として、世界的に知名度は高い。しかし、がんの本態に根本的 な洞察を加ええられただけでなく、がんの治療についてもこのような先進的な確固たる考えを持っておられたこ とに、改めて偉大さを思わされる。がん研究が大いに進歩した今日においても、改めて語り、改めて考えるべき 意味を持つ言葉であると思う。 癌化学療法センターの始まりは四〇年近く前に遡る。1971(昭和四六)年に発足したニクソン大統領によるアメ リカのNational Cancer Programを契機に、化学療法研究における国際協力のわが国の受け皿が検討された。 富三先生は、この受け皿機能は、臨床部門との密接な協力や国内の研究機関・製薬企業などとの連携が必 要であることから、「化学療法の研究は、純粋な研究とは分けて考えるべきである」と結論されたと言う。そして 二年後、財団法人癌研究会の中に癌研究所とは別に癌化学療法センターが設置された、と記されている。新 しく設置された癌化学療法センターは、NCIの協力のもとに、化学療法の開発に係る情報、技術、資材の導入 と普及を進め、日本の化学療法の推進に先導的役割を果たしてきた。富三先生の洞察の深さに頭を垂れるだ けである。 全く新しい発想と機能を持つ新規のセンター開設ともなれば、国際的な協力合意に加え、国内での研究機関や 文部省、あるいは製薬企業等との合意、資金の調達など、超えるべき高いハードルが多く、超人的努力が払わ れたことは想像に難くないが、困難さを伝える記述は見当たらない。人々の記憶の中にしまわれたのであろう か。吉田富三先生は初代の所長に就任されていたが、まことに不幸なことにその竣工式・センター開所式の前 日に奇しくも逝去された、とある。入院中、「開所式には車椅子に乗ってでも出席するよ」と言われていたそう で、さぞかし無念であったろうと偲ばれる。このような、吉田富三先生の化学療法センターに込めた思いを引き 継ぐなど、私などが背負いきれる任務ではないことに改めて思いを致している。 癌化学療法センターはその後、桜井欽夫先生、菅野晴夫先生、鶴尾隆先生へと引き継がれ、化学療法に係る 我が国唯一の中立機関としてその推進に中心的役割を果たしてきた。しかし、富三先生が最終的に目指した 「がん治療の最終手段である」には遠く至っていない。とは言うものの、がんの本態解明は、がん遺伝子、がん 抑制遺伝子の発見と機能解析により大きく進歩し、またヒトゲノムの解析が完了し、その情報を利用する技術も 革命的に進化した。これらを反映して化学療法剤の開発も、細胞障害活性を指標にした開発から一変し、がん 細胞の特性を規定する分子を標的にした開発、いわゆる分子標的治療剤開発へと様変わりした。化合物を見 出し、それがどのように効果をもたらすか調べる時代から、どのように効くかを想定して化合物を見出す時代へ と、発想において逆流した様相である。我が国でも、トランスレーショナルリサーチが声高に叫ばれ、分子標的 治療学会が発足し、いよいよこの変化が主流となってきている。大きく進歩したがん研究に根ざし、化学療法も 新しい時代に入っているようだ。新しい情報化時代の化学療法研究とその推進体制とは、どのようなものであ るべきか、大きく問われているのであろう。 富三先生の考えられたように、化学療法ががん治療の最終的手段であるとすれば、多様な視点からの取り組 み方があり、また必要であろう。しかし、それらの根底には揺るぎの無い確固とした研究が行われなければな らない。この推進こそが基本的に重要なことだと思っている。研究への思い入れ、理屈ではない思い入れが必 要なように思われる。「研究は作業では無い」と言いたくなる機会が多くなったように思われて仕方が無い。そう 言えば、富三先生が腹水がんを移植したマウスを長崎大学から東北大学に運ばれた様子には、先生の研究へ の思いがにじみ出ている。直哉氏の著書から原文を引用してみる。 「(空襲で自家焼失した惨状)・・・佐々木研究所は焼けていなかった。病室で仮眠した富三と佐藤春郎は腹水 肉腫のネズミの籠を分けて持ち、上野へ歩いた。罹災者でごった返す上野からの列車は、石炭車の上から連 結器の上まで乗客が重なっていて、殺人的な混みようであった。その中で四匹のネズミが生き残って仙台に到 着したのである。」 凄まじいばかりの研究への思いである。「今日までの腹水肉腫の植継は奇跡としか言いようがない」と直哉氏 は書いておられるが、富三先生の執念であったとしか思えない。自分が研究に対してこのような思いを持ったこ とがあろうかと、反省させられる。 脱線するが、別の話を思い出した。ロックフェラー大学で研究されていた花房秀三郎先生がFujinami肉腫ウイル ス(FSV)の遺伝子解析をされ、がん遺伝子fpsを発見された。1913(大正二)年、藤浪鑑先生が日本で発見さ れた世界に誇るべきトリ肉腫ウイルスである。アメリカで継代されていたFSVとは別の株を求めて日本の可能性 ある場所を探されたそうであるが、遂に見つからなかったそうだ。ところが、チェコスロバキアの研究所のフリー ザーに保存されていたそうである。花房先生は、「なぜ、この様な貴重な生物試料が、その生まれた国で幻と なる運命をたどったのであろうか」と、日本の科学における体質を嘆いておられた。富三先生のような理屈を超 えた科学への思い入れが、大切らしい。 吉田富三記念館で出会った、もう一つの逸話を思い出す。 「世界ではじめて、特定の化学物質による人工内臓癌の発生を確認したとき、その当事者が興奮しないはずは ない。一刻も早く発表を!と「優先権を競う」気持ちのおこるのが人情であろう。しかし、佐々木隆興、吉田富三 の師弟が偉いのは、「一回の実験は実験にあらず」と、それから追試を重ねたことである。そして、偶然できたこ とではないことを確認したのち、富三は全世界に発表するために「オルト・アミドアツオトルオールの経口投与に よる肝臓癌生成の実験的研究」というドイツ語の論文を書き上げた。当時は医学上の新しい成果は、ドイツの医 学雑誌に発表しなければならなかったからだ。しかし提出すると師の隆興は「ご苦労さま」と言ってそれを机の 引き出しに入れ、見ようともしなかった。茫然としている富三に、「吉田君、実験の成果は一年くらいねかせて、 とり出して未だ値打ちがあったら発表する、それでちょうどいいのだ」と言った。富三はそんな師の全てを学んだ のである。」 物凄い師である。私などは、こんな先生に師事してみたいと言う自信が無くなってしまう。時代のなせる技であ ろうか。さすがの富三先生も茫然としたらしい。「茫然としている富三に」と記されていることに、心安らぐ思いも する。それにしても今の若人が言われれば、無責任とやらパワハラとやら、騒ぎ立てるに違いない。周りもその ように騒ぐであろう。社会の要請という言葉が多く使われ、研究結果がどのように役に立つかをまことしやかに 書くご時勢を、佐々木隆興先生、吉田富三先生はどのように申されるのであろうか。・・・と、ここまで書いて 少々気になったので、吉田直哉氏の著書の中に相当する場所を探してみた。すると、この後にまだ挿話が続い ており、 佐々木隆興は、未だ茫然としている富三に、粉末の五百グラムほどはいったビンを渡して「これは研究所の化 学スタッフが精製し直して、全く混入物の無いことの証明された百パーセント純粋なアゾ色素である」と言った。 そこで初めて、富三先生は混入物の問題があったのだ、と師の意図を理解という。なかなかインパクトの大きい 教育である。理屈をかざさない、この師のやり方に迫力を感じるのは私だけではかなろう。 私が現職に着任した時に、さる先生から次のような言葉をいただいた。「化学療法研究は、副作用の研究が大 切と思います。血球減少は自覚されなくても、味覚の衰えは患者にとっては seriousなものです。」これは、化 学療法研究における臨床部門との強い連携を強調された富三先生の指摘と同じラインであり、化学療法研究 の今後の指標をいただいた気がしてとても嬉しかった。私の友人の言葉を思い出す。化学療法を受けたとき に、「おい、吉田、効くとか効かないとかじゃないよ、死んだほうがましなくらいだ」と。化学療法の研究と推進 を、どのようなやり方で、どのように図るべきか、新しい答えを見つけたいと思っている。 「吉田君、君のしたことは机の引き出しに入れておいて、何年間か寝かせて取り出してみた時に価値があるか どうかだ」と、偉大な先輩に言われるのであろう。さて、引き出しに入れることが出来そうなものを考えよう。 (全文4691文字) |