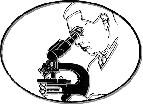
|
||||||
|
平成30年度吉田富三賞を受賞して
東京大学大学院医学系研究科・教授 宮園 浩平
◼はじめに
この度、日本癌学会の平成三十年度吉田富三賞を受賞するにあたり、浅川町吉田富三顕彰会、日本癌学会など関係の皆様、これまで私とともに研究に携わってくださった諸先輩、同僚、後輩の皆様に心より御礼を申し上げます。
学生時代から吉田富三先生のご業績は存じ上げていましたが、私が吉田先生の偉大さをあらためて知ったのは、1995年に当時東京の大塚にあった癌研究所の生化学部に着任してからでした。癌研に着任して間もなく、北川知行所長(当時)や菅野晴夫名誉所長から、我が国のがん研究の原点ともいうべき吉田先生の偉大なる業績をお聞きし、深く感銘いたしました。私は癌研では生化学部の部長でしたが、2000年に東京大学医学部の分子病理学教室に教授として着任することになり、かつて吉田先生が在籍された教室に移ることとなりました。私が東大に移った後も菅野先生は「吉田富三先生の想い出」や「病理の百年を振り返って―広々とした病理学―」などの著書を発表されましたが、これらの本を読むたびに、吉田先生がおられた教室で研究・教育を行うことの幸運をあらため感じ、身の引き締まる思いで過ごしてきただけに、今回の受賞は身に余る光栄です。
◼TGF-βとの出会い
私は学生時代から将来はがんの臨床や研究に携わりたいと考え、1983年に当時の東大第三内科の高久史麿教授の教室に入局しました。血液グループに所属しましたが、増殖因子とがんとの関係に興味を持つようになり、1985年にスウェーデンウプサラ大学のカール-ヘンリック・ヘルディン先生のもとに留学しました。いったん帰国し、1986年にもう一度渡欧、また帰国し1990年にもう一度渡欧ということを繰り返したのは、ヘルディン研での研究の面白さに魅了されたからであり、自由に研究をさせてくださった高久先生には心から感謝しております。
ヘルディン研では血小板由来増殖因子(PDGF)をはじめとした増殖因子の研究が行われていましたが、私は多くの細胞の増殖を強力に抑制するβ型トランスフォーミング増殖因子(TGF-β)に興味を持ち研究を始めました。この頃は細胞の増殖調節におけるアクセルとブレーキの重要性が明らかになり始めた頃で、私はがん細胞の増殖のブレーキのメカニズムを明らかにすることに夢を抱き、研究に没頭する毎日でした。
◼TGF-βのシグナル伝達
TGF-βは1980年代に遺伝子のクローニングや細胞生物学的作用の研究が進み、1980年代の終わりからはTGF-βの受容体の同定が世界中で競争となりました。TGF-βシグナルを伝える受容体にはI型とII型の2種類があることがわかっていましたが、その遺伝子ハンティングは難航していました。ようやく1992年になって米国MITのローディシュ博士のグループがII型受容体の遺伝子クローニングに成功しました。私たちはグループにオランダからピーター・テン・ダイク博士を迎え、II型受容体の構造との類似性をもとに1993年にI型受容体遺伝子のクローニングに成功しました。TGF-βには類似した構造を持つサイトカイン(TGF-βファミリー)が哺乳類だけでも30種類以上存在しますが、これらに対するII型やI型受容体のいくつかの同定についても1995年までには完了することができました。
1995年に私が癌研に移った時期はTGF-β受容体の同定から、細胞内シグナル伝達に研究の焦点が移ってきた時期でした。癌研に移った直後からシグナル分子Smadに関する報告が世界中から次々と発表され、教室の体制を整える間にあっという間に取り残されたと焦りを感じたものです。しかしその後は、幸いにも哺乳類では8種類存在するSmadについて、そのシグナル伝達における役割を明らかにすることができ、またSmadにはシグナルを抑制するタイプのSmadがあることを発見するなど、この分野に貢献することができ、1998年にはヘルディン、テン・ダイク両博士とともにNature誌に総説を発表できたことはたいへん幸運でした。
◼癌研で学んだこと、考えたこと
この時期に癌研で研究をさせていただいたことは私にとって大きな意味を持つことでした。私はスウェーデンではタンパク質の生化学研究に没頭しました。これはスウェーデンの伝統的な生化学研究の基盤に支えていただいたものですが、自らの研究ががんの臨床とはやや遠くなっていくことを感じていました。こうした時期に癌研で研究する機会をいただき、最先端のがん研究者、臨床医の方々に接することで、がんの克服のためにはどのような研究を続けたら良いかということを考える貴重な機会となりました。
この頃、TGF-βシグナルの異常はがん化につながることが米国のグループを中心に次々と証明されました。1995年にはTGF-βのII型受容体の異常がリンチ症候群でしばしば見られることが発見され、翌年には18番染色体長腕に存在する腫瘍抑制遺伝子としてDPC4が発見され、その構造がSmadと類似していたことからSmad4と名付けられたこと、Smad4の異常は膵臓がんの50%で見られることが明らかとなったことは、その代表例と言えます。正常の上皮細胞はTGF-βによって増殖を止めることができます。一方で多くのがん細胞はTGF-βによる増殖抑制作用に抵抗性を示します。こうした細胞の中にはTGF-βのシグナル分子の異常が証明できないことも多く、何がスイッチとなってがん細胞がTGF-βによる増殖抑制作用を受けなくなるかが、私たちの大きな疑問となってきました。
◼上皮間葉転換(EMT)
この頃、私がよくきかれた質問は、TGF-βはなぜ「トランスフォーミング増殖因子」として見つかったのかというものでした。TGF-βは正常の線維芽細胞を軟寒天中で培養したさいに、足場非依存性に細胞増殖を促進する因子として見つかりました。TGF-βが強力な増殖抑制因子なら、その同じタンパク質がなぜ足場非依存性の増殖を促進するのかという疑問です。私自身はこの疑問に答える良い方策がなかなか見つからない状態が続きました。
多くの研究者がTGF-βのシグナル伝達機構の解明に躍起になっているときに、米国UCSFのリック・デリンク博士のグループが1994年にTGF-βは上皮細胞を間葉系細胞に分化させる作用があることを発表しました。胎児期の心臓の発生において内皮細胞がTGF-βによってEMTを起こすという報告は1980年代の終わりから発表されていましたが、デリンク博士らの発見がTGF-βがEMTを誘導することを細胞生物学的に明確に示した最初の報告で、現在のTGF-β研究の大きな流れを作るきっかけとなるのですが、発表された当初はその重要性はあまり認識されませんでした。私はこの頃、血管内皮細胞を培養して実験していましたが、内皮細胞にTGF-βを添加すると増殖が停止するのと同時に細胞が丸い形から紡錘形になることを観察していました。これは今から思い返すと内皮細胞にEMTが起こったことによるものです。研究者にはセレンディピティが大切と言われますが、今から思うと私はこの時にはこの重要な所見に全く気付かず見逃していたのでした。
こうした中で大阪医大腎泌尿器科の東治人先生、帝京大泌尿器科(当時)の堀江重郎先生から、あるマウス乳がん細胞株をヌードマウスに移植すると全身に転移する良いモデルがあるのでTGF-βシグナル分子の作用を見てみたいという相談がありました。そこでTGF-βシグナルを抑制するSmad7のcDNAを送ったところ、Smad7を含んだアデノウイルスをマウスに投与すると肝臓や肺の転移が顕著に抑えられることがわかりました。さらにSmad7はTGF-βによるEMTを抑制することがわかり、EMTの抑制が乳がんの転移を抑えると考えられました。この成果を癌学会で発表したところ、村松正實先生からTGF-βのトランスフォーミング活性を説明する重要な知見だというコメントをいただいたことは私にとって最高の喜びでした。
EMTは研究すればするほど複雑で興味深い現象です。最近私たちはデリンク博士との共同研究で、短期間のTGF-β処理ではEMTは可逆性であるが、長期間の処理では不可逆性になることを見出し、さらに不可逆性になるにはAkt-mTOR経路が活性化されることが重要であることを明らかにしました。これらの結果はTGF-βによって活性化されるSmadシグナル以外のnon-Smad経路をいかに制御するかが、がんの治療にも関わってくることを示すものと考えられます。
◼TGF-βと膵臓がん
これらの成果を契機に、東大に移ってからはTGF-βとがんとの関わりについてさまざまな角度から研究を開始しました。がん微小環境との関連では血管やリンパ管新生とTGF-βとの関連について、その多彩な作用について研究を進めました。さらに肺がん、膵臓がん、乳がん、脳腫瘍、腎臓がんなど様々ながんでのTGF-βの作用について明らかにすることができました。ここでは膵臓がんに絞って紹介します。
ヒト膵臓がん細胞PANC-1はEカドヘリンなどの上皮細胞マーカーを発現していますが、TGF-β添加でEMTを起こしEカドヘリンの発現が低下し、代わりにNカドヘリンなどの間葉系マーカーの発現が上昇し、細胞の運動能や浸潤能が亢進します。EMTの進行とともにいくつかのEMT誘導転写因子の発現が上昇しますが、とくに転写因子Snailの強い発現上昇が見られました。一方で細胞によってはTGF-βはSnailを誘導しないものも多く、この違いが何によるものかが大きな疑問でした。私たちはがん遺伝子KRASに注目し、PANC-1細胞でKRASの発現をノックダウンしたところTGF-βを加えてもPANC-1細胞でSnailの発現が上昇せず、EMTが誘導されないことがわかりました。
膵臓がんの進展過程では種々のがん遺伝子やがん抑制遺伝子の異常の蓄積が見られます。この中でKRASの異常は膵臓がんの初期から90%以上で見られることから、これらのがん細胞ではTGF-βの作用が腫瘍抑制から腫瘍促進へとスイッチし、EMTを誘導することで膵臓がんの進展に寄与していると考えられます。膵臓がんの進展に伴い腫瘍組織でのTGF-βの産生量は増加しますが、作られたTGF-βは腫瘍促進因子として作用しているわけです。Smad4の異常は膵臓がんの約半数で見られますが、その異常は膵臓がんの後期で見られ、この頃にはTGF-βは微小環境に働くことで線維化や血管新生、免疫抑制を促進することで膵臓がんの進展をさらに促進すると考えられ、TGF-βが膵臓がんでは腫瘍促進因子として働いていることを強く示唆するものでした。
◼がん転移と組織透明化
2015年に東大システムズ薬理学の上田泰己教授のグループから、組織を透明化することにより臓器レベルから一細胞のレベルまで詳細に形態学的解析を行えることが報告されました。私たちは上田教授らと共同で、この透明化技術を用いてがん細胞の転移のメカニズムを明らかにすることを試みました。標識した肺腺がん細胞をヌードマウスの尾静脈から注射すると1時間後には肺全体にがん細胞が分布します。多くのがん細胞がすぐに死んでしまうもののわずかながら細胞が残って生着し、やがて転移巣が形成されることが観察できました。興味深いことに肺腺がん細胞をあらかじめTGF-βで処理した上でマウスに注射すると、未処理の細胞に比べて、がん細胞が肺組織内で多く生存し、やがて多数の転移巣を作ることがわかりました。このことはTGF-βはEMTを誘導してがん細胞の運動・浸潤能を亢進させるだけでなく、遠隔臓器に到達した後のがん細胞の生存と血管外への脱出も促進することを示すものでした。ヒトのがん転移巣ではがん細胞はしばしばEカドヘリン陽性で、これはがん細胞に間葉上皮転換(MET)というEMTとは逆の現象が起こるためと言われています。私たちの実験でもTGF-β処理によりEカドヘリンの発現が見られなくなったがん細胞が、転移巣ではE
カドヘリン抗体で染まることがわかり、転移巣でMETが起こっていることが強く示唆されました。これらのことはTGF-βのがん転移における多様かつ重要な役割を示すものでした。
◼骨形成因子(BMP)について
既に述べた通り、TGF-βには構造の類似したタンパク質が30種類以上存在します。この中にはBMPが含まれますが、BMPは骨や軟骨の形成を促進する因子として見つかりました。私たちはTGF-βのI型受容体遺伝子を同定した後、BMPのII型受容体や4種類存在するBMPのI型受容体の遺伝子クローニングに1995年までに成功しました。癌研ではがん研究と並行して骨代謝の研究にも注力しましたが、これは面白い研究はがん研究以外でも自由にやって良いという癌研の方針のおかげでした。その後、BMPも多彩な作用を持つことが明らかとなり、私たちはBMPの初期発生や血管・リンパ管新生、神経細胞の分化などに関する研究を展開することができました。
さらに研究を進めていくうちにBMPと前立腺がん、乳がん、大腸がん、脳腫瘍などとの関連を明らかにすることができました。当初はBMPとがんとの間に深い関連があるとは期待していなかっただけに、BMPの研究ががん研究につながったことは私たちにとって望外の喜びでした。中でも脳腫瘍とBMPとの関連はたいへん興味深いものがあります。BMPが脳腫瘍幹細胞の分化を促進することは2006年にイタリアのグループによって初めて報告されましたが、私たちの研究室でも多形性膠芽腫で、BMP
が脳腫瘍幹細胞の分化を促進することを確認しました。その後、脳腫瘍幹細胞に対するBMPの作用は、4種類あるBMPのI型受容体のうちALK-2と呼ばれる受容体で伝達されることや、BMPにより種々の標的遺伝子が誘導されることを明らかにしました。
進行性骨化性線維異形成症(FOP)は小児期から筋肉や靭帯などに骨化が見られる希少難病ですが、その原因はALK-2遺伝子(ACVR1)の点突然変異によるBMP受容体の活性化亢進によることが2006年に米国のKaplan博士らによって明らかにされました。驚いたことは2014年になって、小児の脳腫瘍であるびまん性内在性橋グリオーマ(DIPG)の約20%の症例でFOPと同じACVR1遺伝子の点突然変異が見られ、ドライバー遺伝子として作用することを示唆する結果が世界の3つのグループから同時に発表されたことでした。その後、BMPのI型受容体キナーゼ阻害剤がDIPGにも有効であることを示唆する結果が海外から紹介されています。私たちはFOPの治療目的で理化学研究所のグループと共同でBMPのI型受容体の阻害剤の開発を進め、2016年までに有望な化合物を開発しましたが、予想しなかった展開に私たちも驚いているところです。
成人の多形性膠芽腫ではBMPが分化を促進するのに対し、小児のDIPGではBMPシグナルの亢進が腫瘍の進展に関わるという知見は、一見食い違うようにも見えます。しかしBMPは正常の神経細胞の分化には重要かつ多彩な作用を示すことが明らかとなりつつあり、BMPが脳腫瘍に対して相反する作用を示すことは、決して驚くべきことではないと考えています。
◼おわりに
私がTGF-βの研究を初めて33年が経ちました。TGF-βが当初の想像をはるかに超える極めて多彩な作用を持つこと、BMPのようなTGF-β以上に多彩で興味深い作用を持つサイトカインに出会うことができたことが、長年研究を続ける上でのモティベーションにつながったと思います。
私がスウェーデンウプサラ大学で所属していたルードヴィヒ癌研究所は世界各地にブランチがありました。スウェーデン留学中に、研究所のディレクターでCEOでもあったロイド・オールド先生がニューヨークから視察に来られました。それまで何人もの日本人研究者がオールド研に留学して成果をあげられていたこともあり、先生は私にたいへん好意的に接してくださいました。自分の研究成果を紹介する際に、「今はTGF-βシグナル伝達研究の競争が激しく、強力なcompetitorが何人もいるので負けないように頑張っている」と言ったところ、オールド先生は、「同じ分野で研究をしている人たちはcompetitor(競争相手)ではなくcolleague(同僚)だと思いなさい」と微笑みながらおっしゃいました。私はこの時、そんなことしていたら競争に負けてしまうと内心では反発したのですが、その後、国内外のTGF-βの研究者とサンプルを交換し、多くのことを学ぶに連れて、オールド先生の言葉の重みをずっしりと感じるようになりました。これまでこうした多くの素晴らしい研究者に出会うことができた幸運に、心から感謝しています。
最後になりましたが、吉田富三賞の受賞にあたり、私のこれまでの研究を支えてくださった多くの先輩諸氏、同僚、友人、後輩の皆様にあらためて御礼を申し上げます。