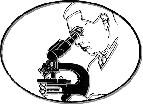
|
||||||
|
令和元年度吉田富三賞を受賞して
はじめに
この度、思いもかけず、令和元年度(第28回)日本癌学会吉田富三賞を受賞する栄誉に浴することとなりました。吉田富三先生の生地である福島県浅川町の江田文男町長、内田宗寿吉田記念館館長をはじめとする一般財団浅川町吉田富三顕彰会の皆様、中釜斉理事長をはじめとする日本癌学会役員の皆様、ならびにご推薦を賜りました間野博行国立がん研究センター・研究所長にこの場を借りて心よりお礼を申し上げたいと存じます。1903年浅川町に生を受けた吉田富三先生はアゾ色素投与による実験的肝発がんに世界で初めて成功するとともに、「吉田肉腫」と呼ばれるラット腹水肉腫を発見・樹立されました。吉田肉腫がその後のがん研究に果たした役割の大きさは計り知れません。我が国のがん研究を世界的なレベルに押し上げた泰斗のお名前を冠する吉田富三賞は、がん研究者にとって敬意と憧れの的であり、これまでの錚々たる歴代受賞者のお名前を拝見しその重みを改めて実感している次第です。以下に、これまでの私のがん研究の軌跡を紹介させていただきたいと存じます。
がんとの出会い
私は北海道の北東部に位置する北見市(昔はハッカ栽培、いまではカーリングで有名になりました)に生まれました。父親は小学校の教師であり、周囲にとりわけ医学を志す環境があったわけではありません。小学校入学直後に両祖父が相次いで胃がんで他界しました。人の死を目の当たりにしたのはこの時が初めてであり、ジワジワと着実に大切な人を死へと追い詰めてくがんという病気に漠然とした憎悪を持ったのはこの時でした。この感情が通奏低音として流れ続けていたのでしょうか、1975年に北海道大学医学部に進学しました。当時の北大医学部では、1950年代の武田勝男先生(病理学)に源を発する腫瘍特異抗原の研究を中心としたがん免疫研究が活発に展開されていました。私は学生時代から、武田門下生のお一人で「がんの異物化」で知られる北大癌研病理・小林 博先生(第9回吉田富三賞受賞)の研究室に出入り、がん免疫研究の真似事をさせてもらっていました。吉田肉腫という名を知ったのはこの時でした(当時は、肉腫という言葉の響きに恐怖感を持ったことを覚えています)。これが、私にとって吉田富三先生との最初の出会いです。
医学部卒業後は、同大医学部付属病院において1年間の臨床研修を積んだ後、大学院(内科学専攻)に進学しました。大学院進学後は第3内科(消化器・血液内科:故宮崎
保教授)に在籍し、白血病を中心とした血液がんの治療に従事しつつ、がん細胞の免疫学的排除をテーマに研究を開始いたしました。このテーマ遂行には、基礎的な研究アプローチは避けて通れないものでしたので、学部時代からお世話になっていた北大癌研病理において小林博教授のご指導のもと、がん細胞を殺傷するT細胞の研究をテーマに研究を始めました。小林先生からはがん細胞の生物学的多面性、可塑性といったしたたかさを理解することががん研究の真髄であると学んだような気がします。
IL-2受容体研究を通した分子生物学との出会い
大学院生としてがん免疫研究を手探りで進める中、当時凄まじい勢いで発展してきた分子生物学的研究を是非行ってみたいという思いが強くなりました。そこで、がん細胞の増殖を抑制するインターフェロンβならびにがん細胞破壊に直接関わるTリンパ球の増殖因子であるインターロイキン2
(IL-2)の遺伝子クローニングに次々と成功し、(財)癌研究会癌研究所(癌研)から大阪大学細胞工学センターに移られたばかりの谷口維紹先生(第17回吉田富三賞受賞)の研究室の門を叩き、国内留学(研究委託)の形でTリンパ球の増殖機構に関する研究に参加させていただけることになりました。谷口先生との出会いは、まさに私のその後の人生を決定づけるものでした。緻密で厳しくも温かい谷口先生のご指導のもと、医学・生物学研究における分子生物学の圧倒的なパワーを日々実感しつつ、多くの才能溢れた共同研究者とともに数多くの満足できる研究成果をあげることができました。なかでも、1989年、国際的にも激烈な研究競争の中、世界に先駆けてヒトIL-2受容体β鎖の遺伝子クローニングに成功した時は、まさに至上の喜びを感じる瞬間でした。
増殖因子からがん抑制遺伝子へ
IL-2によるTリンパ球増殖機構の研究を進めるにつれ、細胞増殖シグナルの異常と細胞がん化との関連、中でもようやくその実態がわかってきたがん抑制遺伝子(がん抑制タンパク質)の役割を細胞増殖シグナルの中でどのように位置づけるのか、という問いに強く心を惹かれました。そこで、ヒトがん遺伝子RASの単離、ヒトがん抑制遺伝子Rbの単離で知られる米国マサチューセッツ工科大学(MIT)ホワイトヘッド研究所のワインバーグ(Robert
A. Weinberg) 先生のもとに留学する機会をいただき、Rbがん抑制タンパク質の機能制御の関する研究に従事することになりました。ワインバーグ先生は既にがんの分子生物学的研究の大巨人であり、普段はとぼけた感じすらするコミカルな人柄の先生が、ひとたび研究者モードに入った時に示す深い知性と創造力には驚愕しました。一見全く異なる2つの事象を直感的に結びつけ、そこに凡人の想像の域を超える新たな論理を構築していく頭脳はまさに圧巻でした。ワインバーグ研で明らかになった成果は以下のように総括されます。我々の体を構成する細胞はRbという強力な細胞増殖ブレーキ分子を保有しており、そのため細胞の増殖は積極的に抑制されています。IL-2のような細胞増殖因子刺激が活性化する細胞内シグナルは、複数の
G1サイクリン依存性キナーゼを順序立てて活性化し、Rbにリン酸化化学修飾を加えることでそのブレーキ機能を破壊する結果、細胞の分裂・増殖が可能になります。このことは逆に、細胞増殖ブレーキとしてのRb機能の失活が、がん化の重要な細胞基盤になることを示しています。例えばある種のDNAウイルスは、Rbと結合しそのブレーキ機能を中和するウイルス由来がんタンパク質を産生し感染細胞のがん化を促します。このがんウイルスとRbの関係は、今回の私の受賞対象となったピロリ菌—胃がん研究を開始する重要なきっかけになりました。1995年、3年半にわたるボストンでの留学生活を終え、当時大塚にあった(財)癌研究会癌研究所(癌研)にウイルス腫瘍部・部長として着任しました。当初は米国の研究スタイルと日本流の研究の違いにやや戸惑いましたが、故菅野晴夫癌研名誉所長(第2回吉田富三賞受賞)、北川知行所長(現癌研名誉所長;第8回長与又郎賞受賞)以下周囲の先生方に支えられ、何とかRb関連の研究を継続して進めることができました。東大病理学時代の吉田富三先生の愛弟子であった菅野先生からは、東大退官後6代目所長として癌研究所を大きく育てあげられた吉田富三先生の業績・思い出・ひととなりを様々な機会でおうかがいできました。菅野先生が吉田先生の思い出話をされる時の誇らしげで嬉しそうなお顔は今も忘れられません。
がん抑制遺伝子からピロリ菌へ
今回の私の受賞テーマは「ヘリコバクター・ピロリ感染による胃がん発症機構の研究」です。IL-2,
Rbと研究を進めてきた私が、なぜピロリ菌研究を始めたのか、その経緯を少し説明させていただきたいと思います。癌研に移って4年を過ぎた1999年、北大免疫科学研究所(現在の北大遺伝子病制御研究所)から教授のオファーをいただきました。しばらく癌研と北大の併任ということで東京と札幌を行き来する日々が続きました。この間、静岡で消化管関連の研究会に招待され講演をする機会がありました。当然ながら、私はRb関連がん抑制遺伝子の機能制御に関する研究成果を紹介したのですが、同じ研究会に参加していた福井医大消化器内科の東健先生(その後神戸大学消化器内科教授に就任されましたが、2017年に61歳の若さでご逝去されました)が、「ピロリ菌が産生する病原タンパク質のひとつ
CagAが胃上皮細胞内に直接侵入する」、という研究成果を発表されたのです。東先生のお話を聞いた瞬間、私はCagAがピロリ菌と胃がんを繋ぐ分子であると確信しました。ウイルスとは異なり、当時ヒトにがんを起こす細菌の存在は知られていませんでした。前述したごとく、ある種のがんウイルスは自らが産生するがんタンパク質を用いて
Rb やp53といった重要ながん抑制分子の細胞増殖抑制効果を不活化し、細胞のがん化を促します。私は、胃上皮細胞内に侵入したピロリ菌CagAもまたRbやp53と結合し、それらのがん抑制機能を不活化すると確信したのです。早速、東先生にこのアイデアをお話しし、共同研究を始めることとなりました。研究開始後数ヶ月間はCagAとRb(あるいはp53)間の結合を検出することに没頭しましたが、何度試みても結果はNoでした。結局、私の直感的な確信は間違っていたのです。しかしながら研究を進めて行くうちに、ピロリ菌CagAと結合するヒト細胞側のタンパク質として発がん性ホスファターゼSHP2が単離されてきました。この発見がピロリ菌による胃がんの発症機構研究にとって大きなブレークスルーとなりました。以下に、その後の北大遺制研時代(2000年−2009年)ならびに東京大学に異動後現在に至る(2009年−2020年)まで進めてきたピロリ菌による胃がん発症機構の成果をご紹介したいと思います。
ピロリ菌と胃がん
ヒトに発症するがんの約20%はウイルスや細菌などの感染微生物に起因すると推定されています。これら感染がんは感染因子の除去ががんの予防・阻止に直接つながるという意味で社会的にもきわめて大きな意義を持ちます。中でも胃がんは全世界がん死亡の約10
%を占める悪性腫瘍です。とりわけ日本、中国、韓国などの東アジア諸国は世界的にも胃がんの最多発地域として知られ、我が国では毎年約12万人が新たに胃がんと診断され、約5万人が胃がんで亡くなるという状況が続いています。MarshallとWarrenによるピロリ菌の発見
(1983年)
に続き、90年代以降の大規模疫学調査ならびに動物への感染実験等を通してピロリ菌感染と胃がんとの関連を示す証拠が蓄積し、現在ではヒト全胃がんの80%以上がピロリ菌により引き起こされると考えられています。こうした状況のもと、「ピロリ菌という細菌の持続感染が胃がんを引き起こす分子機構」の解明は感染がん研究の最重要テーマのひとつとなりました。
ピロリ菌がんタンパク質CagA
ピロリ菌にはcagA
(cytotoxin-associated
gene A)
という遺伝子を保有する株と保有しない株が存在しますが、胃がんに関連するのは専らcagA陽性株です。cagA遺伝子産物であるCagAタンパク質は、菌が保有するミクロの注射針
(IV型分泌機構)
を介してピロリ菌体内から胃上皮細胞内へと直接注入されます。私たちは、胃上皮細胞内に侵入したCagAがSrcファミリーキナーゼによりチロシンリン酸化を受けた後、宿主細胞内に存在する一群のシグナル伝達分子と複合体を形成し、それらの機能を障害する異常な足場
(Scaffold) タンパク質として機能することを明らかにしました。とりわけ、CagAがチロシンリン酸化依存的に結合するSHP2は細胞の増殖・運動をコントロールするRas-MAPキナーゼ経路の活性化分子として知られ、様々なヒトのがんにおいてその活性型型変異や過剰発現が知られる発がん性ホスファターゼです。よって、CagAによるSHP2の脱制御はピロリ菌感染と発がんをつなぐ機構としてきわめて重要な意義を持つと考えられます。CagAはさらに、チロシンリン酸化非依存的に細胞極性のマスターキナーゼPAR1と結合し、そのキナーゼ活性を抑制することで上皮極性を破壊し粘膜構築の崩壊を引き起こします。CagAによるPAR1キナーゼの抑制は微小管の機能障害を介して、細胞分裂期制御異常ならびに染色体不安定性を引き起こします。これら一連の研究成果から、ピロリ菌CagAは胃上皮細胞内に侵入後、チロシンリン酸化非依存的にPAR1を抑制して極性破壊ならびに染色体不安定性を引き起こし細胞の発がん環境を整えるとともに、チロシンリン酸化依存的なSHP2脱制御を介して異常な細胞増殖シグナルを生成し胃上皮細胞の悪性化を促すことが明らかとなりました。
次に、質量分析の手法を用いてCagAの発がん標的であるSHP2の新規基質を網羅的に検索した結果、PAF複合体のコンポーネントの一つParafibrominを同定するともに、SHP2によりチロシン脱リン酸化されたParafibrominが細胞の増殖・分野に深く関与するWnt経路のエフェクター分子b-cateninと結合し、b-catenin/Wnt標的遺伝子群を活性化することを見出しました。さらに、胃上皮細胞におけるCagA依存的なWntシグナルの構成的脱制御が細胞リプロフラミングによる腸上皮化(異分化)を誘導することを明らかにし、胃がんの前がん病変として知られる腸上皮化生の発症ならびに胃がん幹細胞の生成・維持機構の理解に貢献することができました。一方、SHP2の細胞内分布ががん抑制シグナル伝達経路として脚光を浴びる
Hippoシグナルの標的分子TAZ/YAPとの相互作用により調節されることを見出し、SHP2とHippoシグナル間の機能的なクロストークの存在を明らかにすることができました。
ピロリ菌
CagAの発がん活性と分子多型
ピロリ菌CagAの発がん活性を個体レベルで直接検証すべく、cagA遺伝子のトランスジェニックマウスを作製しました。このcagA-トランスジェニックマウスは消化器がんならびに血液がんを自然発症し、CagAは哺乳動物において発がん活性を示すことが直接証明された初の細菌性タンパク質となりました。一方、チロシンリン酸化依存的なSHP2結合部位であるEPIYAモチーフを破壊した変異型CagAを発現するトランスジェニックマウスからは腫瘍性病変は全く発症せず、発がんにおけるCagAのチロシンリン酸化ならびにCagA-SHP2複合体形成の重要性が確かめられました。さらに、マウス体内に誘起される炎症応答は
CagAの存在下で増悪し、この増悪した炎症が翻ってCagAの発がん活性を増大させる結果、炎症局所にはがん化を加速する正のフィードバックループ(発がんスパイラル場)が形成されることが示され、炎症とがんを共役する新たな分子機構の存在が明らかとなりました。一方、東アジアにおける胃がん多発の原因を追求する過程で、CagAのSHP2結合部位となる
EPIYAチロシンリン酸化モチーフが地理的な分子多型を示すことを見出し、胃がんが多発する日本、中国、韓国に特異的な東アジア型CagAは欧米型CagAに比べより強力にSHP2と結合/活性化することを明らかにしました。CagAが示すSHP2結合能の差異が、東アジアにおける胃がん多発の一因となっている可能性が強く示唆されます。また、欧米型CagAにおいては、EPIYAモチーフの重複がCagAのSHP2結合能を飛躍的に増強することを見出しました。
ピロリ菌CagAの構造生物学的解析
CagAの三次元構造解明は、その発がん促進活性をより深く理解するために多くの有益な情報をもたらすと考えられました。そこで、大腸菌を用いた組換えCagAタンパク質の大量精製系を樹立し,
X線結晶解析ならびにNMR
によりCagAの三次元構造決定に成功しました。CagAは3つの独立したユニークなドメインからなる領域(N末端側70%)と天然変性構造をとる領域(C末端側30%)から構成されることが明らかとなりました。さらにSHP2や極性制御キナーゼPAR1が結合するC末側領域はN末側領域と分子内相互作用して投げ縄様のループを形成することで、CagAのSHP2結合能が増強することを見出しました。本研究により、ピロリ菌CagAを標的とする薬剤開発を加速するための重要な構造生物学的情報が得られました。
胃がん発症における細菌とウイルスの協調
宿主胃上皮細胞内にピロリ菌
CagAを脱リン酸化する酵素(ホスファターゼ)が存在するならば、その触媒活性を増強することでCagA発がん活性を中和することが可能となります。そこで、ヒト細胞内でCagAホスファターゼとして働く分子の探索を進め、SHP2ホモローグであるSHP1を同定しました。SHP1は
チロシンリン酸化非依存的にCagAと結合し、CagAのチロシンリン酸化モチーフである
EPIYAモチーフを特異的に脱リン酸化します。SHP1と
SHP2は構造的な相同分子であるにも関わらず、
SHP2がCagAの下流エフェクターとして発がん促進に寄与するのに対し、SHP1はCagA活性を阻害する上流のレギュレーターとして働くことが明らかとなったわけです。さらに、Epstein-Barr
virus (EBV)
感染を受けた胃上皮細胞では、ウイルスが引き起こすエピジェネティックなサイレンシングによりSHP1の発現が強く抑制され、CagAの発がん活性がより増強することを見出しました。胃がん患者の約10%では、ピロリ菌とEBVが共感染していることが知られています。上述した研究成果は、細菌とウイルスが連携してがんを引き起こす仕組みを世界で初めて明らかにしたものです。
終わりに
私がこれまでに進めてきた研究は、ピロリ菌がんタンパク質CagAの機能的役割をナノスケールから臨床疫学に至る様々な階層において検索するとともに、得られた成果を統合することで胃がん発症機構の全容解明に迫るものであり、細菌感染がんとしての胃がん発症機構の理解に大きな貢献を果たすことができました。1999年に私がピロリ菌の研究を開始した頃、多くの研究者は胃がんにおけるピロリ菌の役割には懐疑的でした。例えピロリ菌が胃がんに関連していたとしても、その関与はせいぜい「使い走り」程度であり、「真犯人」と考える研究者はほとんどいませんでした。今日では、大多数の胃がんはピロリ菌感染を基盤に発症することが判明しています。これは医学における大きなパラダイムシフトであり、細菌感染がんという新たながん研究領域の創生にも繋がっています。
IL-2による細胞増殖シグナル研究(阪大)、Rbがん抑制遺伝子研究(MIT、癌研)からピロリ菌CagA研究(北大、東大)に至る研究の流れは、私の頭の中では一つの文脈としてスムーズに繋がっています。振り返るに、研究者にとって人との出会いがいかに大切か、ということが思い知らされます。また、その真偽に拘らず、まずは自らの大胆な直感を盲信してみることが時に大きな発見に繋がることも実体験しました。これがセレンディピティー
(努力してきた者にのみ神(天)が与えてくれる幸運)を呼び込む重要なファクターと信じ、吉田富三賞受賞を人生の大きな区切りとし、新たなセレンディピティーとの出会いに向けた研究を続けて行きたいと思っています。
謝辞
本稿で述べさせていただいた研究成果は、大阪大学細胞工学センター、 マサチューセッツ工科大学ホワイトヘッド研究所、(財)癌研究会癌研究所ウイルス腫瘍部、北海道大学遺伝子病制御研究所分子腫瘍分野、東京大学医学系研究科微生物学分野において、多くのスタッフ・大学院生の真摯で弛まぬ研究の中から生まれたものです。ここに改めて深く感謝の意を表します。また研究を進める上で、多大なお力添えをいただいた共同研究者の皆様にも改めて厚く感謝を申し上げます。
最後になりましたが、吉田富三顕彰会ならびに吉田富三記念館の今後の一層のご発展を心より祈念いたしますとともに、同顕彰会を支えてくださる浅川町には一層のご支援を賜りたくお願い申し上げます。また、がん研究のメンターとしてこれまで私を育ててくださいました小林博先生、谷口維紹先生、ならびにロバート・ワインバーグ先生に心より深くお礼を申し上げます。最後に、私が医学研究者になることを誰よりも力強く応援してくれた両親ならびに研究者としての私の人生を二人三脚のように支えてくれた妻と子供達にこの場を借りて感謝したいと思います。