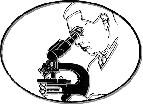
|
||||||
|
令和2年度吉田富三賞を受賞して
慶應義塾大学医学部・教授 佐谷 秀行
■はじめに
この度、令和2年度(第29回)日本癌学会吉田富三賞を受賞するにあたり、江田文男福島県浅川町町長、内田宗寿吉田富三記念館館長、そして一般財団法人浅川町吉田富三顕彰会の皆様、日本癌学会役員の皆様、並びにご推薦を賜りました宮園浩平東京大学大学院医学系研究科教授、間野博行国立がん研究センター研究所長に心から御礼申し上げます。
がんの研究を行うにあたり、その生物学的特性を明らかにし、治療法を立案するためには動物モデルの存在は必須です。吉田富三先生は今から90年以上も前にアゾ色素の経口投与によりラットの肝臓にがんが発生することを発見し、さらにラットの腹水中に浮遊するがん細胞株「吉田肉腫」を作ることに成功され、移植可能ながんの動物モデルを独自に開発されました。そして戦争が終わった直後の厳しい時代に、基礎研究に終わることなく、この細胞を用いて我が国初の抗がん剤ナイトロミンを創生された吉田富三先生の不屈の研究者魂には驚愕せずにはいられません。その偉大な吉田先生のお名前を冠した本賞の受賞の栄に浴しましたことは、がんの研究者としてこれ以上の名誉はございません。吉田先生への尊敬の念と皆様への感謝の気持ちを込めて、これまでの研究の歩みを述べさせていただきたいと思います。
■がん研究を始めたわけ
私は大阪府の泉大津市という繊維産業の盛んな街に生まれ、父は当時毛布を扱う商売を営んでいました。祖父が医師だったことから、医学に興味がなかったわけではありませんが、その当時はアポロ計画をはじめとする宇宙開発やそれを支えるコンピューター技術の進歩が目覚ましく、そんな最先端の研究をする科学者になりたいという漠然とした希望がありました。ともかく私にとっては科学者がヒーローであったことは事実です。高校の時に喘息がひどくなり、それがきっかけとなって勉学に支障が出るくらい体調を崩していたのですが、偶然救急で飛び込んだ医院の先生がその症状をすっかり改善してくださったことから、一気に私のヒーローは医師になり、医学部に進学することを決意しました。
1975年に神戸大学医学部に進学した私は、当時一世を風靡していた手塚治虫先生の「ブラック・ジャック」のようなどんな病気もメス一本で治療する外科医になりたいと思い、卒業するとすぐに脳神経外科教室に入局しました。入局後一年間は外傷や脳梗塞、脳出血のような脳血管障害の患者さんを担当し、救急医療にどっぷり浸かる毎日でしたが、2年目からは脳腫瘍の患者さんを多く担当するようになりました。脳腫瘍の中でも特にグリオブラストーマと呼ばれる悪性腫瘍は手術、抗がん剤、放射線治療と集学的な治療を行っても、ほとんどの患者さんが数ヶ月で再発し死亡するという厳しい疾患でした。グリオブラストーマ細胞は正常の脳の中に深く浸潤するため、たとえブラック・ジャックの手術でも完全に取り除くことは不可能であり、もはや外科の技術だけで解決できる疾患ではないことを思い知らされました。グリオブラストーマがどんな病気なのかを知りたいというごく単純な動機から、大学院への進学を決意しました。
■橋本嘉幸先生との出会い
悪性脳腫瘍を治療したいという情熱は強かったのですが、具体的な研究手法が分からなかったので、脳外科の教授であった松本悟先生にご相談したところ、「君が勉強したいと思う教室があれば、自分で門を叩いてみなさい」とご指導いただきました。そこで、図書館でCancer
Researchという雑誌を一年分取り出してきて、そこに論文を発表している日本人研究者を片っ端から探しました。今考えるとあまりに失礼で汗が噴き出ますが、その先生方に「自分は脳腫瘍の研究をしたいので国内留学させていただけないか」と往信面に書いた往復ハガキを送り、返信を待ちました。奇跡的に一通だけお返事があり、それは東北大学薬学部の橋本嘉幸先生からでした。万年筆で「私たちの研究に興味があればご来仙ください」とだけ書かれていましたが、その返信ハガキを読んだ時の熱くこみあげてくる嬉しさは今も忘れることができません。
次の週に生まれて初めて仙台に行きました。薄暗い廊下の奥にある実験室を覗くと私と同じ年代の若者たちが黙々と実験をしていました。橋本先生はその大きな目で僕を直視し、どうして基礎研究をしたいのかと尋ね、僕が脳腫瘍を治したいからと声を震わせて答えると、来月から来ていいよと笑顔で言ってくださいました。私の長きに渡るがん研究の旅路はその日に始まりました。橋本研究室では、当時既にモノクローナル抗体作製技術を確立していて、私は益子高先生のご指導の下、ラット脳腫瘍を特異的に認識するモノクローナル抗体作製プロジェクトに従事しました。益子先生をはじめとする薬学部の研究者の超絶研究技術を学べたことがその後の研究生活に大きな影響を与えたことは間違いありません。橋本先生のお弟子さんたちは、僕たち臨床医よりがんを治したいという気持ちが強く、そんな同僚たちと毎日遅くまで働くことで、研究を進める上で何よりも大切である「モチベーション」を植え付けていただきました。
後に橋本先生は日本癌学会総会会長をお勤めになられ、東北大学をご退官後は吉田富三先生所縁の佐々木研究所所長としてご活躍され、1997年に第6回吉田富三賞を受賞されました。橋本先生は私にとってはあまりに偉大な存在であり、その先生が受賞された吉田富三賞を私がいただくことは畏れ多く、今も信じられない気持ちです。
■UCSFでの研究生活
私は橋本研究室での研究成果に基づき、「同系ラットモノクローナル抗体による種属間共通グリオーマ関連抗原の解析」という題目で学位論文を纏め、博士号を取得しました。大学院4年目に小児脳腫瘍の国際学会が三重県鳥羽で開催され、そこでこの研究成果をポスター発表したところ、米国UCSF脳腫瘍研究センターの星野孝夫教授の目に留まり、ポスドクとして米国に研究にこないかとお誘いいただきました。そして当時脳腫瘍の治療研究で国際的なリーダーであったビクター・レビン教授のもとに留学することになりました。
29歳で留学するまで、一度も海外に出たことのなかった私にとって、サンフランシスコでの生活は必ずしもバラ色ではありませんでした。まずは英語が出来なくて大変な苦労をしました。特に研究室のカンファレンスは厳しく、毎週月曜の午前中に行われるカンファレンスでの発表を乗り越えることが当面の課題であり、そのために週末は発表原稿を作りそれを暗記することに終始していました。また、実験は当時脚光を浴びだした分子生物学の技術を身につけたいと思っていた私の思惑とは裏腹に、細胞と抗体を用いた薬剤スクリーニング系を構築することを責務として与えられ、来る日も来る日も単純なアッセイを行っていました。レビン教授は脳腫瘍細胞を分化させることによって治療できないかと考えておられ、私は様々な化合物を脳腫瘍細胞に作用させて分化誘導を見る実験を担当していたのです。しかし、この胃が痛くなるような試練は、後の私の研究生活を基盤から支える貴重な経験になりました。
チャンスは突然やってきました。1987年のある日、研究室の私のデスクの上に論文のコピーが置かれ、「内容を読んで、説明しなさい」とボスからの走り書きがありました。それはPCRという新しい技術を用いて遺伝病の診断をするという論文であり、UCSFの別の研究室の成果でした。私はPCRが何かも分からなかったのですが、直観的にすごい技術であると感じ、論文を読んでいて心拍数が上がってきたのを今も憶えています。ボスにPCRという技術を説明し、それを行った研究室で学んでくることを許していただきました。昼間は薬剤スクリーニング、夜と週末はPCRという生活が続きましたが、初めてDNAやRNAに触れることのできた私は、次第に自分で研究テーマを構築することの喜びを感じるようになりました。その矢先、レビン先生からランチに誘われ、ヒューストンに行かないかと突然切り出されました。
■人生を変えたMDアンダーソンがんセンターでの生活
テキサス州ヒューストンに在るテキサス大学MDアンダーソンがんセンターは当時アメリカで3番目の規模を誇るがんセンターであり、全米トップを目指して新進気鋭のがん研究者や医師をリクルートしていました。私のボスであるレビン先生は神経腫瘍部門の主任教授としてMDアンダーソンに異動することが決まり、一緒にヒューストンに移るメンバーの一人として私に声をかけてくださいました。ヒューストンはサンフランシスコとは全く違う環境でしたが、腰を落ち着けて研究に専念することができ、私の人生を変えた6年間であったといえます。UCSF時代に培ったPCRを用いた様々な実験技術はMDアンダーソンで役立ち、多くの研究者との共同研究が進みました。また、Assistant
Professorに昇格し、自身で抄読会を主催したところ、優秀な若手研究者や大学院生が集まってきてくれ、ラボがとても賑やかになりました。熊本大学から留学してきた西徹先生(現桜十字八代リハビリテーション病院院長)はRT-PCRから直接DNA配列を決定する技術を確立してくださいました。また外科のフェローであったケネス・タナベ先生(現ハーバード大学教授)が大腸がんの手術検体を用い、その悪性度とCD44のスプライス変化が相関することをRT-PCRとDNAシーケンシングで検出した成果はランセット誌に発表することができ、それを端緒としてCD44分子との長い付き合いが始まりました。
MDアンダーソンでは若輩ながらPI(研究責任者)として仕事をすることが出来たので、研究計画の立案、研究員の指導、論文の作成・投稿、研究費申請書の作成など貴重な経験を積むことができました。p53やNF1などがん抑制分子の変異解析を行ううちに、それら変異した遺伝子を細胞に導入することで生物学的な意義を探索したいと思い、トランスフェクションの実験を盛んに行うようになりました。今はゲノム編集技術などを用いて自由自在に遺伝子の発現や不活化を行うことが可能になりましたが、30年前はまだ行える研究室は少なく、ワインバーグ研で最先端の分子生物学を学んできたミェンチー・ハン博士(現台湾中國医薬大学学長)に教えていただきながら、細胞が遺伝子によって形質変化していく様を学ぶことができました。そしてそんな研究を楽しんでいるときに熊本大学から、新設された腫瘍医学講座の教授として帰ってこないかというありがたいお話をいただきました。
■細胞分裂研究からがん幹細胞研究へ
1994年1月、37歳になったばかりの私は熊本大学医学部に赴任しました。古く暗い校舎の研究室でしたが、臨床講座の先生方が多くの若い医師たちを送り込んで下さり、研究室はあたかも不夜城のような賑やかさでした。遺伝子クローニングが花盛りの時代だったので、ショウジョウバエに腫瘍を形成する遺伝子群のヒトホモログの同定とその機能解析を若手医師たちと共に行い、AuroraやWartsなど細胞分裂を制御する遺伝子の重要性に開眼しました。オーロラキナーゼの調節機構にかかわる研究で成果を上げた私たちは、2004年に米国ニューポートで開催されたゴードンカンファレンスに出席し、そこで「細胞分裂の異常は本当にがんを誘導できるか」という本質的な命題を突き付けられ、大きく研究の方向性を転換することになりました。
遺伝子改変マウスやレトロウイルスを用いた遺伝子移入実験を行い、細胞分裂異常を導入した時にがんが誘導できるかを試しました。しかし仮説はことごとく否定され、細胞分裂異常をきたした正常細胞は速やかに体内で排除され、腫瘍を形成するには至りませんでした。試しにMycや変異型Rasなどがん遺伝子として知られている遺伝子を同じ手法で導入するとまたたく間に発がんし、それらドライバーと言われる遺伝子の凄さを実感しました。これら遺伝子導入の実験を通して、がん組織を形成する「種」にあたる細胞、つまり幹細胞の成立ががん化には重要であることを、身をもって知ることになりました。
正常の組織は幹細胞を起源として出来てくる細胞によって構成され、幹細胞から永続的に細胞が供給されることで組織が維持されていることが知られています。がんという組織にもこのような幹細胞に相当する起源細胞、つまり「がん幹細胞」が存在することがヒトの白血病で1997年に証明されました。がん幹細胞は乳がんなど固形癌にも存在し、しかも治療に対して抵抗性であることが分かり、これこそが私の求めていた再発や転移の種になる細胞ではないかと考えるようになりました。ちょうどこの頃、基礎研究で見出した所見を臨床に展開して治療抵抗性のがんを駆逐することが最終目的であると考えていた私に、アカデミアにおける基礎から臨床への橋渡し研究が芽を吹き始めていた慶應義塾大学医学部よりお声がけいただき、異動することになりました。
私の今回の受賞テーマは「がん幹細胞を標的とした治療戦略の開発」です。以下に慶應大学において行ったがん幹細胞に関する研究内容についてご紹介したいと思います。
■CD44vのがん幹細胞における機能
2003年頃より固形がんの代表的ながん幹細胞マーカーとしてCD44が取り沙汰されるようになりました。MDアンダーソン時代に手掛けたCD44の研究は、代々担当した大学院生が頑張ってくれていたことから、継続してその機構解析を進めていましたが、CD44がスプライス変化することによって発現するCD44バリアント(CD44v)の生物学的意義は長きに渡り不明でした。それでも粘り強く解析を続けていた永野修先生(現慶應義塾大学准教授)と石本崇胤先生(現熊本大学准教授)らは、CD44vががん幹細胞に発現していて、その治療抵抗性機構に直接かかわっていることを見出しました。
がん細胞は増殖やその生命維持のために多くのエネルギーを産生し、その過程で大量の活性酸素が細胞内で作られます。活性酸素は細胞機能を傷害する毒として働き、がん細胞は活性酸素から身を守るために活性酸素を減少させる能力を持つことが知られています。通常、抗がん剤や放射線などのがん治療は細胞内の活性酸素を高めて細胞死を誘導することを利用していることから、活性酸素を減少させる能力はとりもなおさず治療に対する耐性能を反映することになります。私たちはCD44vを発現するがん細胞では特にこの活性酸素抑制機能が高いことを見出しました。CD44vは細胞膜上でxCTと呼ばれるシスチンを取り込むポンプ分子とくっついてxCTの機能を高め、大量のシスチンが細胞内に流れ込むことでシスチンを原料にしてグルタチオンが産生されることが分かりました。グルタチオンは強力な抗活性酸素分子であるため、CD44vを発現しているがん幹細胞は治療に対する抵抗性を発揮することが明らかになりました。つまり、CD44vあるいはxCTの機能を抑制することで治療抵抗性を解除することができるのではないかと考えました。
■ドラッグリポジショニングによる治験の実施
私たちはがん幹細胞を標的とした治療を行うにあたり既存の薬剤を用いることができないか考えました。20年以上前から私たちは既に認可されている薬剤を集めたライブラリーを構築していて、具体的な標的分子が見つかった時にはそれらの薬剤の中に標的を特異的に阻害するものがないか探そうと考えていました。スルファサラジンという30年以上前から潰瘍性大腸炎および関節リウマチの治療薬として用いられている薬剤がxCTに対して阻害効果があることを見出し、それを用いてマウスモデルによる動物実験を行いました。動物実験ではスルファサラジンがCD44v発現がん細胞を特異的に駆逐することが分かり、国立がん研究センター東病院と共に胃がん患者さんに対する臨床試験を計画しました。このように既存の薬剤を用いて行う治療を今はドラッグリポジショニングと呼びますが、私たちが実施した当時は極めて斬新なアプローチでした。
11例の患者さんに投与を行い、4例において有意にCD44v陽性細胞が減少していることは確認できましたが、残念ながらがんそのものを縮小させることはできませんでした。がん幹細胞を刈り取ることができても、通常のがん細胞を駆逐できない限り癌を本格的に治療することができないことが分かりました。そこで、通常の抗がん剤治療にスルファサラジンを上乗せする医師主導治験を九州大学と共に行うことにいたしました。手術不能の進行性肺がん患者さんと対象として実施し、がん縮小後の再増大までの期間を有意に延長することができました。
治験の結果からスルファサラジンを用いた治療にはある程度の手応えを感じることはできましたが、やはり根治を目指すには毒性を上げずにさらに効果を上げるための基礎研究に戻らなければならないと考えました。そこで、スルファサラジンに対する抵抗性細胞を用いて更なる薬剤スクリーニングを実施し、スルファサラジンにあと1剤追加することで抵抗性細胞を特異的に殺す薬剤を探索しました。その結果、アルデヒド脱水素酵素(ALDH)を阻害する薬剤が選ばれ、スルファサラジンと併用することでがん細胞特異的に劇的に活性酸素を上昇させ多くのがん細胞を効果的に駆逐することが明らかになりました。2つの異なる分子を同時に阻害することで治療抵抗性細胞を駆逐するこの2剤併用のアプローチは概念的にも新しく、現在臨床応用を目指して治験を計画しています。
■人工がん幹細胞
吉田肉腫の存在が抗がん剤ナイトロミンの開発に繋がったように、治療法の開発にはヒトのがんを模したモデルは必須です。私はもともとグリオブラストーマの治療を目指して基礎研究の世界に身を投じましたが、1990年代当時世界中のどこを探しても私が臨床で経験したグリオブラストーマの病理像と臨床像を反映する動物モデルは見当たりませんでした。グリオブラストーマの患者から樹立した細胞株は、マウスの脳に移植しても実際のグリオブラストーマのような病理組織像を呈することはなく、長年そこに大きなフラストレーションを感じていました。がん幹細胞の概念を学ぶにつれて、腫瘍組織はがん幹細胞から生まれてくる種々のがん細胞が、周囲の正常組織と相互作用することによって構築される有機体であり、本物のがん組織を構築するためにはがん幹細胞から出発したモデルを作らなければならないという考えが私を支配し始めていました。折しも神戸大学の同窓である山中伸弥先生が熊本大学にセミナーに来て下さり、彼がマウスの正常細胞に4つの遺伝子を導入することによって万能細胞iPSを作製することに成功したことを知り、同様の手法を用いることによってがん幹細胞も作れるのではないかと考えました。
マウスから取り出した組織幹細胞や前駆細胞に遺伝子改変を行い、特殊な培養と移植を繰り返すことで、がんの種である人工がん幹細胞(iCSC)を作製することができました。研究室の皆さんの努力により、白血病、骨肉腫、肺がん、胆管がんなどに加えて、念願のグリオブラストーマのiCSCも出来上がりました。わずか10個程度のiCSCをマウスの脳に移植すると、ヒトのグリオブラストーマの組織と酷似した複雑な腫瘍組織が成立し、すべてのマウスがほぼ同じ時期に同じ症状を呈するというモデルが出来上がりました。これらiCSCは免疫系が正常なマウスに100%腫瘍を形成することができて、免疫治療の標的としても使用できることから、既に多くの研究者に使っていただいています。今後、私たちが作製したiCSCが新しい治療の開発に役立てばこんなに嬉しいことはありません。
■分化誘導治療との邂逅
骨肉腫のiCSCを用いて解析を行ったところ、その形成された腫瘍組織の中に増殖能は低いが治療に対する抵抗性が高く、極めて未分化な細胞が存在することを見出しました。この細胞こそが治療後に残存して再発の種となる「真のがん幹細胞」であると考え、その治療法を考案したいと思いました。この細胞は通常の抗がん剤ではとても駆逐することはできませんが、未分化な性質を逆手にとり、分化誘導するという戦略を考えてみました。私がUCSFでひたすら行っていた分化誘導実験のアイデアがここで役立ちました。ちょうど研究室の信末博行先生が、アクチン細胞骨格を薬剤で脱重合させることによって間葉系幹細胞を成熟した脂肪細胞に分化させることができるという成果を発表したところだったので、その概念をiCSCと融合させて、がん幹細胞の脂肪細胞への分化という実験を計画しました。果たして、抗がん剤投与後に残存したがん幹細胞は脂肪細胞に転換し、マウスに形成された骨肉腫を有意に縮小させることができました。この薬剤も既存薬であることから、ドラッグリポジショニングによる臨床への応用が今後期待できます。
■おわりに
がん幹細胞の概念が導入されたことで、がんの発生、再発、転移はがん幹細胞を起源として生じることが明確になりました。またこれまで、がん治療は増殖能の高い細胞をせん滅すればよいという考えから、がん幹細胞のような比較的増殖能は低くても治療耐性能の高い細胞を標的にして対応しなければ根治できないという考え方に変わりました。実に大きなパラダイムシフトであり、40年近くに渡る研究生活でその知識と技術が醸成される過程を現場で見ることができたことを、何よりの幸福と感じています。
がん幹細胞は私たちが殲滅すべき憎き敵ではありますが、その生存戦略には学ぶところが多く、知れば知るほど組織のリーダーとしての振舞いに感心させられます。特に周囲の環境や侵襲(治療)を感知して形や性質を即座に変える可塑性・柔軟性と、細胞内を常に浄化させて恒常性を保つ機能は優れていて、敵ながらあっぱれと言わざるを得ません。このような可塑性や恒常性維持機構を破綻させるためには医学研究者だけの力では難しく、これからは分野を超えた研究者の叡知を結集する必要があると考えます。今回の受賞はこれからも研究を続けなさいという激励のメッセージであると思い、使命を遂げるために他分野の研究者たちと協力しながら、引き続き頑張りたいと思っております。
最後になりましたが、浅川町、吉田富三顕彰会および吉田富三記念館の益々のご発展を心からお祈りいたし、私のがん研究の旅路の記録を残す機会をお与えいただきましたことに感謝申し上げます。また、私のメンターであり恩人である松本悟先生、橋本嘉幸先生、星野孝夫先生、ビクター・レビン先生に心から御礼申し上げます。そして、本稿で述べさせていただいた研究成果は、神戸大学脳神経外科、UCSF脳腫瘍研究センター、テキサス大学MDアンダーソンがんセンター、熊本大学腫瘍医学教室、慶應義塾大学医学部先端医科学研究所遺伝子制御研究部門の皆さんのご尽力なくしてあり得ませんでした。皆さんと一緒に仕事ができたこと本当に幸福に思います。そして私を長年にわたって支えてくれた家族にこの場を借りてお礼を述べたいと思います。