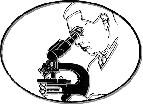
|
||||||
|
令和5年度吉田富三賞を受賞して
はじめに
この度は、令和5年度(第32回)日本癌学会吉田富三賞受賞の栄に浴し心より御礼を申し上げますと共に、福島県浅川町町長・一般財団法人浅川町吉田富三顕彰会理事長、江田文男様、吉田富三記念館名誉館長、内田宗寿様、一般財団法人浅川町吉田富三顕彰会の皆様、また佐谷秀行理事長を初め日本癌学会役員の皆様、さらに今回ご推薦をいただいた金沢大学医薬保健研究域医学系呼吸器内科学の矢野聖二教授に深謝申し上げます。吉田富三賞と申しますと、日本のがん研究者にとってはこの上ない栄誉でありまして、30年上前にがん研究を始めた当時にまさか、自分などがそのような賞をいただけるなどとは全く想像もできませんでしたので、この度の受賞に際して感謝と同時に身が引き締まる思いが致しております。吉田富三先生の人工発がんや継体可能ながん細胞株の樹立に関するご研究は、発がんのメカニズムの理解や、がんに対する治療薬開発におけるその後の研究に関する極めて大きなブレークスルーでありますが、これらの研究成果は、現在の私の研究のテーマであるがんの進化の研究においても大きな貢献をされました。そうした吉田富三先生ががん研究に残された大きな足跡に思いをいたしつつ、私自身のこれまでの研究について少し紹介をされていただきたいと思います。
がん研究に
先ほど、「これまでの研究について紹介を」と申し上げましたが、思い返してみますと、もうすでに35年近く医学に携わってきて、これまで自分の研究の履歴を振り返るというようなことをしたことがありません。そういう余裕もなく今日にいたったというのが実感です。そもそもなぜがんの研究を志すようになったと申しましても、なにかの研究をしたいという特段の強い希望があったわけではなく、また人並み以上の志があったわけでもありませんから、医学部を卒業して臨床研究をおえて東京大学医学部第三内科に入局して以来今に至るまで、がんの研究に関わることになろうとは1982年に東京大学に入学した当時には想像もしていなかっように思います。そのような私ががんの研究をやってみようと思い立ったのは、やはり医師となって多くの患者さんの診療に携わることになり、病気の悲惨を目にすることは大きなきっかけになったように思います。とくに白血病をはじめとするがんで苦しむ患者さんの診療に携わるようになると、「なぜこのような病気がおこるのだろう、いつかこのような病気を治すことができる日が来るのだろうか」と。もちろん、研修医とはいえ、医師として病気と向き合うわけですから、まるで分からないわけでもない、それどころか、当時は分子生物学が興隆して、今まで分かりようもなかった病気の性質というものが、少しずつ遺伝子や分子のレベルで説明されるようになってきた時代でしたから、上の疑問は、やがて、「どうしたら白血病が起こるメカニズムを分子の言葉で説明ができるようになるか、そしてもしかしたら幸運にも新たな治療法が見いだされるかもしれない」という興味に変わるようになりました。
1990年前後のがん研究の風景
当時、自分がもっとも興味を引かれたのは、がんでは染色体の異常が生ずるがそれらは全くでたらめではなくて、同じような異常がことなる患者でも繰り返し認められること、また同じ異常をもった白血病には共通した特徴、表現型が認められることでした。このような異常のなかで最も古くから知られていたフィラデルフィア染色体とよばれる異常は、9番染色体と22番染色体の間で相互転座の結果生ずる異常で、転座によって9番染色体上コードされているABLという遺伝子と22番染色体上のBCRと名付けられた遺伝子が融合した異常な融合遺伝子が形成されて、その結果生ずるBCR/ABL融合蛋白が産生され、この蛋白が有する異常なチロシンキナーゼ活性がこの染色体の出現を特徴とする慢性骨髄白血病(CML)と呼ばれるがんの発症に関わっていること、が示されていました。また、このような繰り返しみとめられる染色体の変化によって生ずる遺伝子の異常が白血病やその他の発がんに関わっているという研究が次々に報告されるようになっていました。ですから、染色体の異常ががんの原因になっているのではないかということは、当時まだ研修医の私にとっても容易に想像できました。細胞の形質を子孫の細胞に伝えるゲノムの異常ががんの原因になっている、ということは大変に腑に落ちる話で、したがって、その結果生ずる蛋白質の異常を明らかにすれば、がんがなぜ生ずるかということを説明できるだろうというわけです。実は、このような考え方は、遺伝子が染色体を形作るゲノムのDNAによって担われているというこが明らかになる数十年前、20世紀初頭に遡るのですが、いずれにしても、当時研修医として白血病や悪性リンパ腫という血液のがんの診療に携わる中で、染色体の転座や、増加、欠失、点突然変異、など細胞のゲノムに生ずる異常を明らかにすることが、がんを理解する上では極めて本質的であるだろう、だから将来、がんの研究をするとすれば、そのような研究がしたいかな、と考えるようになりました。
大学院とc-Crk研究
そんなわけで、私が血液内科学を専門として当時の東京大学第三内科に入局して最初に与えられた、「マウスc-Crkのクローニングとその機能の解析」には、分子生物学の技術を習得するという以上に殆ど興味を持つことができませんでした。もっともこのようなテーマを与えられたのは、当時、がん研究の大きな潮流が、新たながん関連遺伝子の発見と並んで、ウィルス発がんの研究に端を発したシグナル伝達機構の研究と表裏一体をなして展開していたからでした。すなわち、がん遺伝子として当時同定されていた遺伝子の多くが、チロシンキナーゼのシグナルの伝達に関わる分子をコードしていたからでした。私が与えられたc-Crkはトリ肉腫を生ずるウィルス中に発見されたv-crkの細胞相同遺伝子で、チロシンキナーゼ活性は持っておらず、その機能の制御に関係したSH2、SH3と呼ばれる構造だけからできている蛋白でした。しかし、その遺伝子の異常がヒトの発がんに関わっている証拠はなく、その機能の研究を通じてヒトのがん、まして白血病の病態
を理解をすることは大変迂遠に思えたからでした。とはいえ、c-Crkの研究に携わった1990年から1993年にかけての研究経験は、後年、発がんのメカニズムを遺伝子の機能から理解する上で、大変貴重な経験となりました。
がんゲノムの研究
研究の一つの転機となったのは、1994年、Nature誌に、様々なヒトのがんで欠失が認められる染色体9p21領域の責任領域から、サイクリン依存性キナーゼ4阻害因子として知られるp16をコードする遺伝子を同定したとする報告でした。現在でいうところにCDKN2A遺伝子で、この遺伝子はサイクリンD1に依存して細胞周期を負に制御しており、その機能的喪失によって細胞増殖を抑制する仕組みが破綻することが発がんにとって重要であることを示唆する発見でした。早速ヒトの白血病でこの遺伝子の異常を調べてみたところ、急性リンパ性白血病で頻繁にこの遺伝子がホモ接合性欠失を来していることが分かりました。現在においても、TP53遺伝子とならんで、ヒトのがんでもっとも頻繁に異常が認められる遺伝子ですが、ヒトのがんゲノムの解析によってがんが生ずるしくみが明らかになることを示す研究成果で、あらためてがんゲノム解析の重要性を示す結果でした。そこで、急性リンパ性白血病その他のリンパ系腫瘍の他、様々なヒトのがんで頻繁に染色体欠失が認められる6番染色体長腕の欠失領域から新たながん抑制遺伝子の同定を試みることにしました。1996年から始めたこの研究はしかし、大変困難を極めました。振り返ってみると理由は明らかでした。がんゲノムを解析するという基本的な方法論には疑いはありませんでしたが、時代があまりに早すぎたということです。このような研究を、ゲノム解析の知識も、経験も、リソースも乏しい環境で遂行するというのは無謀だったかもしれません。当時、ヒトゲノム計画は漸く始まったばかりで、ヒトゲノムのマーカーも整備されておらず、6qの欠失領域といってもまるで広大な平野を詳細な地図もなしにさまよい歩くというような状況でした。多型マーカーがまばらに点在するといった感じで、マーカーとマーカーの順番すら危ういもので、どこに遺伝子がコードされているかも分からず、当時漸く頒布されていたBACライブラリーを自分達でスクリーニングしながらプローブを作成して、多数の白血病・リンパ腫細胞株における欠失領域をFISH方でスクリーニングするという地道な作業を繰り返し、漸く狭められた数メガベースの領域をショットガンシーケンスで配列決定をして、そこから蛋白がコードされている領域を探してくるという、本当に気の遠くなるような作業を繰り返しました。その後、そのようにしてともかくもPRDM1あるいはBLIMP1が責任遺伝子の一つであることを見いだし、マウスモデルの解析も進めていたのですが、残念なことに、これはニューヨークのColombia大学のグループによって先に報告されてしまいました。長年にわたって大変な労力をかけて行ってきた研究でしたので大変残念でもありました。
SNPアレイを用いたゲノムコピー数の解析
そうした困難な状況にあっても、しかし、がん病態の理解を進めるには、ともかくもヒトのがんで生じているゲノムの異常を明らかにすることとが重要であるという考えは全く揺らぐことはありませんでした。ただ問題は、そのために必要な十分な知識や技術の基盤が十分に整っていない状況で、こうした解析をわずか数人のグループで進めるにはあまりに困難が大きかったということでした。大きな転機は、ヒトゲノムのドラフト配列の決定とマイクロアレイ技術の登場によってももたらされました。まだかなり不完全であったとはいえ、2003年、ヒトゲノムの完全シーケンスが公開されたことはゲノム研究に携わる研究者には革新的な出来事でした。研究者たちは遂にヒトゲノムの地図を手にすることができました。これによって、今、自分たちが30億塩基対もあるゲノムのどこを解析しているかということがわかる様になったと言うことです。さらにより大きな進歩は、この広大な領域を系統的に解析することを可能にする新たな技術が登場したことでした。高密度にプローブを配置した商用マイクロアレイです。それまでは、数千個のBACクローンからDNAを調整し、これをつかってスライドガラスの上に自前でDNAをスポットするというようなことをやっていたのですが、これは大変労力と時間のかかる作業で、また、作成したアレイの品質も不安定でしたので、なかなか安定した結果をうることが困難でした。ところが、Affymetrix社から発売されたマイクロアレイは、ゲノムワイド関連解析を可能とする目的で開発された高密度オリゴヌクレオチドアレイで、基板上に高密度に化学合成された多数の一塩基多型(SNP)プローブを用いて、ゲノム全体で250〜500万個の一塩基多型を同時に決定することができるという画期的なアレイでした。我々は、もともとSNPタイピング用に開発されたこのアレイを用いてえられるSNPのシグナルが高い定量性を有することに着目して、がんのDNAをSNPアレイで解析し、我々自身が開発したCNAGと命名した独自の解析プログラムを用いて、がんで生ずるゲノムの増幅や欠失、あるいはアレルの不均衡といった様々な異常を、微小な異常を含めて検出することができるようになりました。2004年〜2005年にかけてのことです。高い品質で作成されたアレイを用いるとことにより、多数のがん試料を従来では考えられないような高いスループットと精度で解析することが可能となり、がんゲノムの解析研究は大きな転機を迎えました。例えば従来あれほど困難を極めていた6qの欠失領域の解析にも新たな展開がみとめられ、ホジキンリンパ腫その他の悪性リンパ腫においてBLIMP1に加えて、A20というNFkBシグナルの制御を司る蛋白をコードする遺伝子TNFAIP3遺伝子の欠失や変異が生じていることを当時大学院生であった加藤元博君が明らかにしてくれました。6qの欠失は複数の遺伝子標的があり、また腫瘍においても異なる遺伝子が標的となっているというわけで、それまで想定したようなp16を標的する9p21の欠失とはまったく状況がことなっていたということも判明しました。また、解析の高いスループットを生かして様々ながん種の解析にも取り組むことができるようになり、東京大学小児科の林泰秀先生、滝田純子先生たちとの共同研究を通じて、ALKキナーゼの増幅や変異が神経芽腫における重要な原因となっていることを明らかにした他、以下で述べる骨髄異形成症候群の病態解明においても大きな成果が得られました。我々の開発したCNAGはSNPアレイを用いたゲノムコピー数解析に広く使用されるようになり、様々な海外の研究者と共同研究をする機会に恵まれました。それまで、東大の小さな研究室の隔絶した研究環境からは得られない大きな資産となりました。
骨髄異形成症候群の研究
骨髄異形成症候群(MDS)は形態の異常をともなった原因不明の血球減少と急性骨髄性白血病(AML)への移行を特徴とする難治性の血液がんの一つですが、その分子病態は長く不明でした。MDSにおける遺伝子異常の研究では、私が東京大学第三内科に入局して以来ご指導をいただいた高久史麿先生、平井久丸先生らが世界に先駆けてNRAS遺伝子の異常、続いてTP53遺伝子の異常を報告されていたほか、RUNX1遺伝子の変異が明らかにされていましたが、2000年の時点では多くの症例で原因となる遺伝子の異常は不明でした。この研究分野においても、SNPアレイ解析技術は大きな転機をもたらしました。すなわち、我々は11番染色体のLOHの集積領域の解析からCBL遺伝子の変異を、また海外の複数のグループから、TET2遺伝子やEZH2遺伝子の変異がMDSで高頻度に生じていることが報告されました。
一方、SNPアレイの開発に続いて、がんゲノムの研究には、さらなる革新がもたらされました。2009年ごろから我が国でも漸く利用可能となった次世代シーケンス技術です。これはゲノムDNAを超音波処理によって得られる数百万個のDNA断片をマイクロアレイ上に固定し、アレイ上でDNA伸長反応を一塩基毎逐次的に行い、この過程を顕微鏡下にCCDカメラで撮影することで、新たに取り込まれる蛍光標識した塩基を検出することで、数百万カ所について塩基配列を決定するという大量並列技術で、まさに塩基配列決定技術における革新でした。やがてアレイ上のクラスターは数百万から数十億に高密度化され、いまや一回の実験で数T
(10^12) bpの塩基配列データが得られるまでに至っています。この技術は、およそ医学研究のあらゆる領域に革新的な進展をもたらしたことはいうまでもありませなんが、がんの研究においては絶大な威力を発揮することになりました。その後10年足らずで、殆ど全ての主要なヒトのがんについて、その発症に関わっている頻度の高い遺伝子異常の解明が一気に進みました。我々も、この新たなシーケンス技術を用いて様々ながんのゲノム異常の解明を行いました。最初に取り組んだのは、多年にわたる課題であった骨髄異形成症候群のゲノム解析でした。29例のMDS患者さんの検体を用いてそこで生じているゲノムの異常を解析することにより多数の新たな遺伝子変異を世界で初めて同定することに成功しました。もっとも印象深かったのは、一群のRNAスプライシング因子に高頻度にみとめられた変異でした。遺伝学の中心的な理論では、ゲノムDNAに書かれた遺伝情報は、いったんRNAに転写された後、イントロンとよばれる領域が除かれてmRNAとなり、これを鋳型として蛋白質が合成されることによって、遺伝情報が発現するというものですが、RNAスプライシング因子は、このイントロンの除去に携わる細胞にとって不可欠の機能を担う一群の蛋白質です。私達の発見は、なんとこのRNAスプライシングを担う少なくとも8つの主要な因子、とくにSF3B1、SRSF2、U2AF1、ZRSR2と呼ばれる4つの因子に集中的に生じており、MDSの60%内外でいずれかの因子の変異が認められるというもので、当時研究室に参加したばかりの大学院生であった吉田健一君が見いだしてくれた重要な発見でした。RNAスプライシング因子という人知では容易に想像できなかった遺伝子群に高頻度に変異発表と同時に世界中から称賛のメールをいただいたのを記憶しています。RNAスプライシング因子はMDSの他、急性骨髄性白血病(AML)や骨髄増殖性疾患(MPN)においても頻繁に観察されることから、これらの変異は骨髄系腫瘍の発症において基本的に重要な役割を担っていることが明らかとなりました。次世代シーケンス技術を用いた遺伝子変異の解析は極めて有効で、我々はこの発見に続いて、コヒーシン複合体の変異やBCOR/BCORl1遺伝子の変異など、MDSの原因となっている一群の遺伝子を同定し、また、ドイツの研究者と共同して1000例近いMDSの症例の解析を行うことにより、MDSで生じている遺伝子変異の全体像を明らかにすることができました。2000年代までの苦労は一体何だったのかと思うほど、技術革新が新規発見に及ぼす効果を痛感しました。近年では、MDSゲノム研究の国際コンソーシアムの共同研究を通じて、遺伝子変異を加味したMDSの新たな予後予測モデルを構築し、これは現在国際標準として広く世界のMDS診療に寄与しています。
京都大学への異動と次世代シーケンシングを用いたがんの病態解明
MDSにおけるRNAスプライシング因子の変異を最初にNature誌に報告して以降、次世代シーケンスを用いて様々ながんの発症に関わるゲノム異常の網羅的な解析を始めました。京都大学からお誘いをいただき、現在の腫瘍生物学講座に移ったのもこの頃でした。教授の職を得たことについては、殆ど感慨はありませんでした。それより、東京大学での時限付きの講座では身分の心配もしなくてはいけませんでしたので、身分の心配をする必要なく研究に集中できるということはありがたいことでした。まだ東京大学に在籍していた頃から、研究に参画してくれる意欲のある若い先生たちがだんだんと増えてくるようになりました。泌尿器科から来ていた佐藤悠祐君と血液内科出身の吉里哲一君は、統合的なゲノム解析を通じ淡明細胞腎がんのゲノム異常の全容の解明を明らかにし、これはTCBE1変異によって特徴づけられる新たな淡明細胞腎がんの発見に結びつきました。スプライシング因子の変異を発見した吉田健一君は、さらに、弘前大学の伊藤悦朗先生たちと共同で、多年にわたって病態の不明であったダウン症候群由来の急性巨核球性白血病の解析を通じてコヒーシン変異をはじめとする一群の変異が本症の発症に重要な役割を担っていることを報告してくれました。また、鈴木啓道君は、大規模なゲノム解析によって世界ではじめて、低悪性度神経膠芽腫におけるゲノム異常の全体像の解明を行い、この研究は現在のWHO分類にも反映されています。また京都大学に移る前後から研究室に加わった片岡圭亮君は、我が国が主要な流行地であるHTLVIウィルスによって惹起される成人T細胞白血病(ATL)のゲノム異常の全体像を解明してくれました。これは、世界の多くの研究者から高い評価をえることができたATL研究のランドマーク研究と考えられています。また、片岡君は、ATLのゲノム解析を進める過程で、その約1/4の症例で、免疫チェックポイントをコードするPD-L1遺伝子が遺伝子再構成によって高発現を来して免疫回避を生じていること、同様の遺伝子再構成は他の癌種においても広くみとめられがん免疫からの回避のメカニズムとなっていることを明らかにしてくれました。また、最近では、藤井陽一君が尿路上皮がんのゲノム解析を通じて同腫瘍の新たな分子分類を構築し、またこれ基づいて尿を用いた非侵襲的な診断法を開発してくれました。さらに、竹田淳恵さんは、私自身が研修医時代からずっと興味を持ち続けていた急性赤白血病の発症機構の研究から、この赤血球系に分化する傾向の強い白血病が、TP53遺伝子の変異とエリスロポエチンの高度増幅と変異によって特徴づけられることを明らかにしてくれました。
がんの初期発生の研究 -がんの起源の研究-
京都大学に異動してから始めた研究は、がんの起源に関するものです。これは、まだ東京大学にいた2011年くらいから始めていた再生不良性貧血における遺伝子変異の研究に端を発したものでした。再生不良性貧血という疾患は、自己免疫によって造血細胞が破壊される結果、血球を産生することができない病気で、免疫抑制療法や造血幹細胞移植が開発されるまでは、大変に予後の悪い疾患でした。この病気に対する興味を持つようになったきっかけというのは、まだ研修医のころに、自治医大から東京に帰る電車の中でJudith
Marshという方がBritish Journal of Hematologyに書かれた再生不良性貧血という疾患に関するコメンタリーをたまたま読む機会がありました。この疾患は自己免疫の機序で生ずるけれども、しばしば染色体異常が認められる、さらに、免疫抑制療法が奏功しても、数年ののちに、しばしば骨髄異形成症候群や急性骨髄性白血病を発症する、ということが書かれていました。自己免疫疾患だけどクローンなの?どういうこと?すぐには了解できない話でありました。そういうわけでしたので、再生不良性貧血の患者さんの血液で遺伝子変異が認められるかどうか、吉里君に調べてもらったところ、なんと急性骨髄性白血病や骨髄異形成症候群でしばしば認められる遺伝子変異が再生不良性貧血においてもしばしばみめとられることが明らかになりました。丁度この研究を行っていた2013年の春、ハーバード大学のBenjamin
Ebertという友人を訪れた際に、このことを発表したところ、彼は健常人でも高齢者ではそうした変異が認められるということを発見していました。彼らの研究は我々の研究に先立って2014年にNew
England Journal of Medicine誌に報告され、つづいて翌年、私達の研究成果も同誌に掲載されました。これらの研究成果が示すところは、加齢にともなって我々の造血組織には、白血病や骨髄異形成症候群でみとめられるのと同様に遺伝子変異を獲得して選択されたクローンによる造血が生ずることがあり、これは再生不良性貧血のような慢性炎症下では促進されるということです。健常人の血液にすでに白血病の変異がみとめられるということは、考えてみるともっともな話でした。つまり、がんはいきなり発症するわけではなく、そうした変異が徐々蓄積する結果、やがて十分な異常が生じて白血病や骨髄異形成症候群を発症するという風に理解されます。実際、クローン性造血を有する人はそうでない場合に比べて有意に白血病や骨髄異形成症候群を発症します。
こうした発見に触発されて、京都大学に移ってからは、正常組織における遺伝子変異の研究に着手しました。はじめは半信半疑で。最初に発表できた成果は、横山顕くんがやってくれた正常食道における遺伝子変異の研究です。大変驚くべきことに、我々の食道は加齢にともなって、食道がんで頻繁に認められる遺伝子変異を獲得した数万個の異なるクローンによってパッチワークのように覆われるようになり、65歳を過ぎるころには、食道全体の6割から8割の領域がこのようなクローンによって再構築されること、この過程はすでに幼少期ないし思春期にはじまり、飲酒や喫煙といった食道がんの良くしれられリスクによって促進されることが明らかとなりました。続いて、消化器内科医の垣内伸之君は、潰瘍性大腸炎の患者さんの大腸上皮も、クローンによって大きく再構築されることを明らかにしてくれました。そこでは、大腸がんでしばしば認められる遺伝子変異の他に、潰瘍性大腸炎の発症に重要な役割を担っているとされているIL17のシグナル伝達経を司る遺伝子に多数の変異が生じていることがわかりました。このことは、潰瘍性大腸炎では遺伝子変死によってIL17のシグナルが伝わらなくなった細胞が炎症によって破壊された上皮の再生に寄与すること、一方、がん遺伝の変異を獲得した細胞によって発がんが促進されることを示唆していました。
このように、正常組織は加齢や炎症、飲酒や喫煙の影響をうけて、それぞれの環境に適応した細胞が選択されて、体細胞によるモザイクによる組織の再構築が生じること、その一部からがんが生ずることが明らかとなってきました。このようないわゆる「体細胞モザイク」はがんの初期発生過程を理解する上で重要な手がかりを与えてくれるのみならず、我々の生態が加齢その他の影響をうけて大きく再構築されるということは、それが加齢や炎症に伴う臓器の機能の変化と密接に関係している可能性を示唆しています。こうして、発がん研究は今や、加齢その他の人疾患の研究に展開しつつあります。
おわりに
冒頭では、「少し紹介させていただきます」ということでしたが、気がついてみるとちょっととりとめの無い話になってしまいました。発がんの研究は、がんにおける体細胞変異の研究から、いまや正常組織における体細胞モザイクの研究にまで発展しつつ新たな展開をみせています。研修医のころに漠然と考えていた発がんのメカニズムからは随分と遠いところにきてしまいました。そうこうしているうちに、京都大学で私の残された研究期間はわずか4年となってしまいました。これまで研究していて一体どれくらいがんという病気を理解できたでしょうか。月並みな話ですが、新しいことがわかっても、もっとたくさん分からないことができてしまう。人生は短く芸術学問は長し、でしょうか。現在は、発がんの研究から少しはなれて、新たな治療薬剤の研究に取り組んでいます。今後とも吉田富三賞の何恥じることなく、がんの理解に少しでも貢献ができればと考えています。