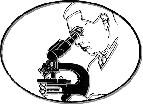
|
||||||
|
平成28年度吉田富三賞を受賞して
東京大学分子細胞生物学研究所 秋山 徹
はじめに
日本癌学会の平成二十八年度吉田富三賞を受賞する栄誉に浴し、身に余る光栄です。アゾ色素による肝細胞癌の発生、吉田肉腫の発見等によるがん細胞生物学の創始、さらには日本初の化学療法剤ナイトロミンの開発をはじめとした化学療法の開拓など、がん研究に偉大な足跡を残された吉田富三先生のお名前を冠した賞を受賞することとなり恐縮しております。須藤一夫理事長(浅川町長)を始めとした浅川町吉田富三顕彰会の皆様、宮園浩平理事長を始めとする日本癌学会役員の先生方に深くお礼申し上げます。ここでは、十月八日における日本癌学会吉田富三賞受賞記念講演の内容をかいつまんでご紹介させていただきたいと思います。
がん遺伝子・チロシンキナーゼ
1980年代は癌遺伝子のクローニング隆盛の時代で、次々にいろいろな癌遺伝子がクローニングされました。東京大学医科学研究所の豊島久真男先生の研究室ではチロシンキナーゼをコードする癌遺伝子を中心に数々の重要な遺伝子がクローニングされました。一方で、それらがどのような機能をもつタンパク質をつくって、どのようなメカニズムで細胞の癌化を引き起こすのかについては、十分な理解が得られていなかったと思います。そこで私は、癌遺伝子のつくるタンパク質を同定してその機能を明らかにするという当時の大勢とは異なるスタイルで研究に取り組むことによりこの状況を打開し、細胞癌化のシグナル伝達機構の実体を明らかにしようと試みました。例えば、山本雅先生がクローニングした上皮増殖因子受容体(EGF)受容体遺伝子と類似したErbB2遺伝子のつくるタンパク質の実体がチロシンキナーゼ活性をもつ受容体型膜タンパク質であることをタンパク質側から明らかにしました。さらに、EGF受容体やErbB2タンパク質のチロシンキナーゼ活性の制御機構をタンパク質レベルで明らかにし、EGF受容体やC-kinaseとのリン酸化を介したシグナル伝達機構が存在することなどを示しました。また、Fgrなどの非受容体型チロシンキナーゼに関する研究を進め、さらにがん遺伝子cotの産物がセリン・スレオニンキナーゼであることを明らかにし、その機能を明らかにしました。この成果は、後にCotタンパク質がMAPKKKであることの発見に結びつきました。
現在では、細胞膜受容体に発するシグナルが細胞内で伝達される機構の詳細が明らかになり、さらにこのシグナル伝達を阻害する分子標的薬が開発されて成果をあげていることはご存知の通りです。ErbB2やチロシンキナーゼの研究に携わりながら、自分たちの手でハーセプチン(抗ErbB2モノクローナル抗体)やグリーベック(チロシンキナーゼ阻害剤)などのような分子標的薬を生み出せなかったことを大変残念に思っています。大分前ですが、文科省の癌特別研究の会議中、高名なアドバイザーの先生が「ハーセプチンが日本で開発されなかったのは言語道断である!」と発言されたことは忘れられません。もちろん何もしていなかった訳ではなく、益子高先生、遠藤啓吾先生との共同研究では、抗ErbB2モノクローナル抗体ががんの画像診断や治療に有用である可能性があることを示す実験結果を得ておりました。遠藤先生のもとには全国から100種類くらいのモノクローナル抗体の有用性を調べてほしいという依頼がくるとのことでしたが、「その中でものになりそうなのは一つか二つしかないんですけど、この抗体はその一つか二つですよ」とのことで是非臨床を目指したいと話しておられました。ところが、複数の企業がかかわっていたことも良くなかったのですが、その中の1社が事故が起きたら困ると言いだして結局開発取りやめとなってしまいました。今思えばもっとやりようがあったように思われますが、当時は抗体がこれほどの良い薬になるとは誰も思っていなかった時代で、信念に欠けていたのかと思います。もっとも、ある大手製薬委企業の方にこの話をしたところ、「当時の日本の製薬企業でハーセプチンのような薬をつくるのは所詮無理でしたよ」と言われたことがあります。
チロシンキナーゼについても、製薬企業から微生物の培養濾液をいただいて、阻害剤のスクリーニングを進めました。セリン・スレオニンキナーゼ阻害作用は大変弱く、チロシンキナーゼの活性を特異的に阻害する化合物を単離して論文にしたところ非常に良く引用されました。もっと良い化合物をさらにスクリーニングすべきだったのですが、製薬企業からは「チロシンキナーゼは免疫、脳などでも重要な役割を果たしているので副作用が強いはずだから良い薬になる可能性はない」と言われ却下されました。当時のチバ・ガイギーのグリーベック開発者と話した時にこのことを話したところ大変驚かれ、良い薬になるはずだから自分達は開発を続けると言われました。当時は現在の「次世代がん」のような組織もなく孤立無援という感じで諦めざるをえませんでしたが、自分が日々取り組んでいるような仕事からグリーベックのような素晴らしい薬が誕生する可能性がある(ハードルは高いが)ということがわかりました。今は「次世代がん」の支援を受けていますので、何とかリベンジしたいと思っています。
癌抑制遺伝子APC・Wntシグナル
1980年代後半になって長い間実体のわからなかった癌抑制遺伝子がクローニングされはじめました。前々から癌抑制遺伝子に興味を持っていたので、早速癌抑制遺伝子のつくるタンパク質の機能の実体を明らかにすることに取り組みました。まず網膜芽細胞腫の原因遺伝子Rbがクローニングされたので、遺伝子産物に対する特異抗体を作製し、RBタンパク質を同定しました。さらに、RBタンパク質が松本邦弘先生の同定した細胞周期のG1期からS期への進行を引き起こす役割を担うサイクリン依存性キナーゼの基質であることを見出しました。
さらに、1991年には、中村祐輔先生が家族性大腸ポリポーシスの原因遺伝子APCをクローニングされ、APC遺伝子は散発性の大腸癌でも高頻度に変異が見出されることを明らかにされました。そこで、早速cDNAをいただいて遺伝子産物の機能解析を始めました。これまでに見たこともない構造のタンパク質をコードしていることから、APCタンパク質の機能を解析することにより、まったく新しい癌化のメカニズムが明らかになるのではないかと期待しました。ところが、あっという間に米国のグループから、APCが形態形成に必須の役割を果たすWntシグナルの伝達因子であるβ-cateninに結合して分解を誘導することにより、Wntシグナルを抑制することが報告されました。大腸癌で見いだされる変異APCタンパク質はβ-カテニンの分解を誘導できないため、細胞内にβ-カテニンが蓄積して、転写因子TCF/LEFと相互作用して、癌遺伝子c-Myc等のWnt標的遺伝子の転写を促進して細胞増殖の亢進を引き起こすと考えられました。
一方、私たちのグループは、APCに結合するタンパク質を網羅的に検索して、Axin、hDLG、KAP3、Asefなどの重要なタンパク質がAPCと複合体を形成していることを見出しました。大腸癌でみられるAPCの変異は分子の前半に集中しており、変異によって終始コドンが生じて短い遺伝子産物ができることが特徴です。特に、散発性の大腸癌では分子の中央付近に変異が集中しています。従って、変異が起きる領域の下流に重要な分子が結合することがAPCの癌抑制遺伝子としての機能に重要なのではないかと考えました。実際、AxinのAPCへの結合部位を調べてみると、まさしく変異の集中している領域のちょうど下流に位置していました。結局、AxinはAPCやβ-カテニン、グリコーゲン合成酵素リン酸化タンパク質-3β等と複合体を形成してβ-cateninの分解を誘導し、Wntシグナルを抑制する重要な役者であることがわかりました。
興味深いことに、APC遺伝子に変異のない症例では、β-カテニンのアミノ末端領域のリン酸化部位が変異をおこし、安定化が起きている場合があります。したがって腺腫ができるためには、APCに変異がおきてβ-カテニンの分解がおこらなくなるか、β-カテニンが変異を起こして安定化すればよいと考えられます。しかし、大腸癌でのβ-カテニンの変異は症例の数%にしか見出されず、ほとんどの症例でAPCの変異が見出されることや、小さい腺腫に比べて大きい腺腫や癌ではβ-カテニンの変異の見つかる頻度が低いことなどから、APCにはβ-カテニンの分解誘導以外にも重要な機能があると考えることができます。私たちは、Asefと名付けたRhoファミリーの低分子量G蛋白質に対するヌクレオチド交換因子の一種が、変異により断片化したAPCに結合して活性化し、細胞の形態、接着、運動を制御していることを見出しました。さらに、APC-Asef複合体はHGF、EGF、VEGF等のシグナルの下流で機能し、細胞運動の活性化に関与していることを明らかにしました。さらに興味深いことに、APC-Asef複合体はこれらの因子の刺激を受けて血管内皮細胞の運動能を高め、血管新生に重要な役割を果たしていることがわかりました。従って、Asefは癌細胞と血管内皮細胞との両方で重要な役割を果たしており、実際APCに変異があって腸管にポリープの多発するマウスにAsefノックアウトマウスをかけあわせると、ポリープの数が激減しました。Asef阻害剤は大腸癌の分子標的薬として有用である可能性があると考えられます。
この他、APCが機能を発揮するためには細胞の先端やラッフリング膜に局在する必要がありますが、細胞先端への局在はAPCがアダプタータンパク質KAP3を介してモータータンパク質KIF3A/3Bに乗って微小管上を移動することによって起こることを明らかにしました。興味深いことに、大腸癌で発現している変異APCは細胞先端にクラスターをつくることができません。また、APCはショウジョウバエの癌抑制遺伝子として知られるDlgのヒトホモログと結合して細胞周期を制御していることを明らかにしました。
また、Wnt
シグナルの抑制因子ICAT、活性化因子B9L、β-カテニン-カドヘリン複合体の輸送に関わるRICS等の新規分子を同定しWntシグナルの制御機構を明らかにしました。
長鎖非コードRNA
最近になって、ヒトゲノムの大部分の領域からタンパク質をコードしない長鎖非コードRNAが大量に転写されていることがわかってきました。非コードRNAの中でも、20-30塩基の小さなRNAについてはいろいろなことがわかってきていましたが、200塩基以上の長鎖非コードRNAと癌化の関係についてはほとんど明らかになっていなかったので、試しに造腫瘍性の強い大腸癌細胞で発現の亢進している長鎖非コードRNAを50種類ほど選んでRNA干渉(RNAi)法を用いて発現を抑制してみました。驚いたことに10種類ほどの長鎖非コードRNAの発現を抑制すると癌細胞が死んでしまうことがわかりました。そこで、癌細胞の生存に必須でありながら機能未知の長鎖非コードRNAの機能に取り組むことにより、新たな癌化の分子機構が明らかとなり新しい創薬への道が開けるのではないかと考えました。現在では、長鎖非コードRNAが、細胞の増殖、分化、癌化、発生、神経機能、幹細胞性の維持等様々な生物学的プロセスにおいて重要な役割を果たしていることが明らかになってきています。特に、癌との関係では、HOTAIRのように転写制御に関与するものがよく知られています。ここでは私共が解析した長鎖非コードRNAのうちからいくつかについて機能をご紹介します。
UPATと命名した長鎖非コードRNAは、アミン酸化酵素の一種の偽遺伝子なのですが、驚いたことに発現を抑制すると大腸がん細胞はヌードマウスに腫瘍を造る能力が顕著に減少してします。そこで、UPATの正体を明らかにすべく解析を進めたところ、UPATがDNAメチル化やヒストン修飾を介して転写を制御するエピゲノム制御因子UHRF1タンパク質と結合し、ユビキチン化酵素によるタンパク質分解誘導からUHRF1を守ることによってUHRF1を安定化し、大腸がんの増殖や腫瘍形成を促進していることが明らかになりました。またUPATは、SPRY4及びSCD1と呼ばれる遺伝子の発現を誘導することによって大腸癌細胞の増殖を引き起こしていることがわかりました。
MYUは、Wnt/c-Myc経路の標的として見出した長鎖非コードRNAで、ほとんどのヒト大腸がんで多量に発現しており、やはり大腸癌細胞の増殖に必須の役割を果たしていると考えられました。MYUの機能を解析した結果、MYUはRNA結合タンパク質hnRNP-Kと複合体を形成して、細胞周期を進める機能をもつサイクリン依存性キナーゼの3’側のタンパク質をコードしていない領域(3’UTR)に結合して、microRNAの機能を阻害することによって、その発現の上昇を引き起こしていることを突き止めました。
ASBELは、癌抑制遺伝子ANA/BTG3のアンチセンス鎖にコードされており、核内でANA/BTG3
mRNAと2本鎖を形成して細胞質への移行を阻害し、卵巣癌の造腫瘍性を促進することがわかりました。さらに、大腸癌ではASBELはWntシグナルにより直接転写が活性化され、やはりWntシグナルの標的である転写制御因子TCF3タンパク質と結合してATF3の遺伝子座に結合し、ATF3の発現を抑制することにより、大腸癌細胞の増殖を抑制することがわかりました。
タンパク質と複合体を形成して機能する長鎖非コードRNAには、microRNA等と違って統一的な作用機序、作動装置といったものはなく、それぞれが独自のメカニズムで独自の機能を果たしているようです。これら以外にも、デコイとして機能したりする非コードRNAなど様々な機能をもった非コートRNAが見つかりました。
造腫瘍性に重要な遺伝子の網羅的探索と1細胞解析
最後に今現在興味をもって進めている研究についてごく簡単にご紹介させていただきます。
これまで、RNAiライブラリーを用いてがん幹細胞の造腫瘍性に重要な遺伝子を探索し、分子標的薬開発の基礎研究を進めてきました。現在は、CRISPR/Cas9システムを用いて癌細胞の〜2万遺伝子をノックアウトすることにより、造腫瘍性に重要な遺伝子をさらに網羅的に検索し、取得した遺伝子の機能を解析しています。
もう一つの関心事は1細胞解析です。これまでの研究によって癌組織は極めて多様な細胞からなることが明らかになってきました。癌組織には癌幹細胞や分化して造腫瘍性の低下した癌細胞や様々な正常細胞が含まれています。これらの多様な細胞を1細胞ずつ油滴の中に封じ込め、バーコード標識することにより、個別の細胞ごとの遺伝子発現の解析が可能になってきています。例えば、卵巣癌は通常4種類に分類されていますが、そのうちの明細胞癌を1細胞解析すると、遺伝子発現パターンの異なる4種類の癌細胞から構成されていることがわかりました。これらの細胞群は、それぞれが特徴的な遺伝子を発現しており機能が異なると考えられます。このような解析により、癌組織の多様な癌細胞集団から造腫瘍性、転移能、制癌剤耐性度等の異なる細胞を単離し、丸ごとの解析では平均値の中に埋もれていた悪性度に寄与する遺伝子を同定することが可能になると考えられます。また、1細胞毎の遺伝子の発現だけでなく、転写因子の結合状態やヒストン、DNAの修飾状態を解析する手法の開発も進める必要があります。
おわりに
宮園浩平癌学会理事長と癌細胞の多様性について議論していた時に、吉田富先生が「癌細胞には個性がある」という言葉を残されたということを教えられました。私たちは今その「癌細胞の個性」を分子の言葉で理解して、その知見をもとにした癌の新しい治療法を考案することが可能である地平に辿り着いたのかもしれません。今後、「癌細胞の個性」の分子的理解に基づく新しい分子標的薬の創製に取り組みたいと考えております。最後に、これまで共同研究をしていただいた沢山の先生方、ラボメンバー、そしてご指導いただいた豊島久真男先生、山本雅先生に心からお礼を申し上げたいと思います。