癌研究の先駆者 吉田富三
人工肝臓がんの生成
吉田富三は、明治36年2月10日、福島県浅川町に生まれた。成長した富三は、やがて東京帝国大学医学部に進み、卒業後、病理学を専攻、東京の佐々木研究所に入所した。
ここで富三は、所長の佐々木隆興博士の指導を受け、化学物質(アゾ化合物)の経口投与によるラット(シロネズミ)の肝がんの発生に成功した。昭和7年、世界で最初の人工肝臓がんの生成である。この研究は後に、イギリスのE・L・ケナウェイらの研究と共に、発がん性化学物質究明の糸口となった。

吉田肉腫の発見
富三はその後、長崎医科大学に赴任(昭和13年)、第二次世界大戦という困難な時代の中、地道に研究を続けていった。そうして昭和18年6月、富三は、発がん実験中のラットの腹水中に、浮遊するがん細胞「吉田肉腫」を発見することとなった。
腹部が膨張したラットの腹水を顕微鏡で見ると、おびただしい数のがん細胞が観察された。その液体を注射針にとり、次のラットに腹部注射すると、やがてそのラットの腹部も膨れて液体が溜まった。その液体を再び顕微鏡で観察すると、がん細胞が一個一個バラバラに液体の中に浮いて増殖し、活発に細胞分裂している姿があった。移植の成功である。この発見は、がんの主役ががん細胞であり、がん細胞は移植が可能であることを示すものであった。これにより研究者たちは、がん細胞だけを自由に取り扱えるようになった。新しい、細胞レベルでのがん研究の幕開けである。
この腹水がん(腹水腫瘍)は、はじめ腹水肉腫と呼ばれていたが、後に長崎系腹水肉腫(昭和21年)と命名された。昭和24年、日本癌学会総会で「吉田肉腫」と改称され、その名は世界に広がった。吉田肉腫はがんの研究にとって欠かせない材料となった。富三は国内外の研究者の要望に応え、この材料を惜しみなく分与した。

がんの科学療法へ
顕微鏡を覗き続け「がんは一つの細胞からでも再発する」「がん細胞には個性がある」「がんは全身病である」など、がんの本態を明らかにした富三は、がんの化学療法への道も切り拓いた。
薬物や色素が、がん細胞に障害を与えることに気づいた富三は、吉田肉腫を使って、がんの化学療法に取り組み、昭和27年、日本で最初の制がん剤、ナイトロミンの開発に成功した。それまでのがん治療は外科による手術と放射線照射のみしかなかったが、吉田肉腫が、がんに効く薬物の効果を客観的に測定することを可能にしたのである。これを契機に、がんの化学療法は目覚ましい進歩を遂げることになった。
富三は東京帝国大学(病理学教授、昭和19年)、財団法人佐々木研究所(所長、同28年)、東京大学(医学部長、伝染病研究所教授兼任、同33年)、財団法人癌研究会癌研究所(所長、同38年)などを歴任、生涯にわたってがん研究の先導者としての役割を果たし、昭和48年、70歳で世を去った。富三の研究は多くの医者によって引き継がれ、がん克服の課題に向けて、確かな歩みとして発展している。

吉田肉腫とその後の研究
吉田肉腫の発見
昭和18年(1943年)6月 長崎大学で、吉田肉腫が発見されました。肝発がん実験中のシロネズミ(ラット)のお腹が大きくなり開いてみると白い液体がたまっていた。顕微鏡で見てみるとがん細胞が一杯だった、これは面白い、役に立ちそうだと先生は、その液体を注射針とり、次のねずみのお腹に打ってみた。まもなくそのネズミのお腹がふくれて液体がたまってきた。顕微鏡でみると同じがん細胞がたくさん殖えている。がん細胞は一個一個バラバラに液体の中に浮いて殖えている。細胞分裂も旺盛だ。移植に成功したのである。先生と教室員は、がん細胞の形態や染色体を詳しく研究し始めた。また、薬物や色素ががん細胞に障害を与えることに気づかれ化学療法の研究を開始された。同年、吉田先生は長崎から仙台に転任された。がんを持ったネズミを東京、仙台に無事に移すことに先生がどんなに苦心されたかは吉田直哉さんの本に詳しく記されている。いつ思い出しても感激するお話である。
吉田先生は、長崎系腹水肉腫の名前を使っておられたが、昭和22年の日本病理学会宿題報告でご発表の時、会長の木下良順先生が、吉田先生の名をとって吉田肉腫と呼ぶことを提案、満場一致で賛成され、以来、吉田肉腫と呼ばれて世界の中にその名が広がった。
吉田肉腫の教えたもの
吉田先生と教室員は仙台の東北大学で、また、東京の佐々木研究所で吉田肉腫の研究に励まれて、多くの優れた成果をあげられた。これらをまとめてみると次の二つになると思います。一つは、がん細胞生物学という新しい学問の誕生であり、もう一つは、がん化学療法の誕生であります。それまでのがん研究はがん組織というがんの塊を用いた研究でした。吉田肉腫の発見によって、がんの研究が細胞単位で研究することが可能になりました。細胞分裂や染色体の解析、一粒移植や細胞培養など、がん細胞とはどういうものかを細胞単位で研究する新しい学問、細胞生物学が誕生したのです。吉田肉腫の細胞分裂を顕微鏡映画でとって、目の前でスクリーン一杯にがん細胞が二つに分裂するダイナミックな瞬間に、不可思議ともいえる細胞の美しさに人々は驚いたものでした。そして、映画細胞学(シネサイトロジー)という言葉さえ生まれたのです。
第二のがん化学療法ですが、それまでは、がん治療は外科による手術と放射線照射の二つのみでした。がんに効く薬を確かめる方法がなかったのです。吉田肉腫の発見はそれを可能にしました。ある薬物をある量与えると吉田肉腫は、一定の変化、障害を受ける、といった具合に、薬物の効果を客観的に測定することが可能になったのです。このようにしてナイトロミンという日本最初のがん化学療法剤が開発されました。これを契機に化学療法の進化は素晴らしく、外科、放射線に続く第3の柱としてがん治療に欠くことのできないものとなっています。
吉田肉腫の起源
吉田肉腫の起源はどこか、ルーツは何かとなるといろいろな説がありました。腹腔の単球とする説、腹膜表面の中皮とする説、肝のクッパー細胞説などで、吉田先生も初めは単球かクッパーかと迷っておられたようですが、その後の腹水肝癌や吉田肉腫変異株(LY)の研究によって肝癌由来であろうということに落ち着いておりました。平成5年(1992年)に、吉田肉腫やLYの性質を現在の新しい学問的方法を用いて研究してみることを思い立ち、癌研の実験病理部の樋野興夫博士が実際にやってくれました。
その結果は、吉田肉腫はリンパ球のT細胞の特徴を持つということで、これまでの定説の性格に新しい光が与えられたと申してよいでしょう。平成6年暮れの27日、かつて若き日、吉田肉腫や腹水肝癌に情熱を燃やした佐藤(春)、井坂、杉村の諸先生を初め、オールドソールジャー十数人が癌研の化学療法センターに集まり、その昔にそれぞれが経験し、考えたことを話し合い、ヤングソールジャーの新しい研究結果を聞き、吉田肉腫の起源について討論をしました。吉田肉腫はネズミからネズミへと50年の長い間植え継いできたので、その間、いろいろと変わることもあるだろうから、T細胞の特徴を示すからといってすぐT細胞が吉田肉腫のルーツと断言はできないだろうということになりました。
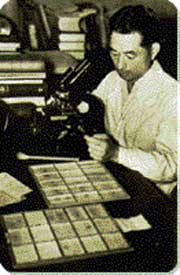
吉田富三博士 年譜
- 1903年(明治36) 福島県浅川町に生まれる。父・喜市郎、母・ナヲ。3子長男。
- 1923年(大正12) 20歳 東京帝国大学医学部医学科入学。
- 1927年(昭和 2) 24歳 同大学卒業。同大学医学部病理学教室副手。
- 1929年(昭和 4) 26歳 佐々木研究所入所。
- 1932年(昭和 7) 29歳 アゾ化合物の経口投与による人工肝がんの生成に成功。
- 1935年(昭和10) 32歳 佐々木研究所退所。ドイツ留学。癌学会山極賞受賞。服部報公会賞受賞。
- 1936年(昭和11) 33歳 恩賜賞受賞(第1回)。肝臓癌成生の実験的研究。 第2回国際会議出席(ブリュッセル)。
- 1938年(昭和13) 35歳 長崎医科大学教授(病理学)。
- 1943年(昭和18) 40歳 ラット腹水肉腫を発見、「長崎系腹水肉腫」と呼ぶ(吉田肉腫)。
- 1944年(昭和19) 41歳 東北帝国大学教授(病理学)。
- 1951年(昭和26) 48歳 日本学術会議会員(第2期)。第13回日本医学会総会で「癌の本態観」の講演。吉田肉腫天覧を賜る。
- 1952年(昭和27) 49歳 朝日賞受賞(吉田肉腫の研究)。東京大学教授(病理学)がん化学療法薬ナイトロミンを開発。
- 1953年(昭和28) 50歳 財団法人佐々木研究所所長「吉田肉腫の病理学的研究」で恩賜賞受賞(第2回)。
- 1958年(昭和33) 55歳 東京大学医学部長・東京大学伝染病研究所教授併任。鉄門会頭。
- 1959年(昭和34) 56歳 文化勲章受章。科学技術会議専門委員。
- 1960年(昭和35) 57歳 日本学術会議会員。
- 1961年(昭和36) 58歳 第50回日本病理学会会長。ペルジア大学(イタリア)より名誉学位を授与。 医療制度に関する吉田メモ発表。国語審議会委員。吉田肉腫移植1000代記念講演会(長崎大学)。 第1回日米科学協力委員会(東京)。
- 1962年(昭和37) 59歳 第9回国際癌会議組織委員会委員長。
- 1963年(昭和38) 60歳 財団法人癌研究会研究所長。日本学術会議会員(第6期)副会長。国語審議会委員。
- 1965年(昭和40) 62歳 故郷の福島県石川郡浅川町より名誉町民の称号を授与される。
- 1968年(昭和43) 65歳 日本ユネスコ国内委員会副会長。
- 1971年(昭和46) 68歳 第18回日本医学会総会で特別講演(癌の成長)。
- 1973年(昭和48) 70歳 逝去。勲一等旭日大綬を授与される。